閑話休題13 『現代思想』の「ロシア革命100年」特集への批判
閑話休題13 『現代思想』の「ロシア革命100年」特集への批判
塩原俊彦
この閑話休題8、9で立て続けに「ロシア革命100周年」に絡む所感をのべた。実は、そのころに『週刊金曜日』の編集者からこの問題に関する原稿を求められたために、もう一度改めて「ロシア革命」について考える必要に迫られていたのである。なお、この拙稿は12月22日に刊行される『週刊金曜日』に掲載される。お読みいただければ、幸甚である。
権威主義への嫌悪
そのために「ロシア革命100年」という特集を組んだ『現代思想』を購入し、読んでみた。まずなによりも、思想を上から権威主義的に押しつけるやり口に強い違和感をもった。『現代思想』そのものが権威主義的であることによって、その存在感を保っているのだろうが、もはやそんな権威主義は通用しない。「社会主義」なるわけのわからぬイデオロギーに加担しながら、「ロシア革命」なるものに関心を寄せてきた「似非学者」にいまさらなにを語らせようというのだろうか。
和田春樹はこの雑誌の対談で、「社会主義ユートピアの挫折は、1991年のソ連の崩壊によって、ついに誰の目にも明らかになりました。しかしながら、平和を求める反戦・反軍の民衆的ユートピアは、20世紀をとおして実現されることはありませんでしたが、21世紀にいたるまで力を失っていません」と語る。
きわめて不可思議なのは、「ユートピア」思想そのものの問題点を探ることなく、安直にユートピアを受け入れる姿勢だ。ユートピアに絡む「デザイン思考」の陥穽に気づかなければ、ロシア革命の本質を剔出し、それを批判することなどできない。こんな分析しかできないから、ロシア革命の全体主義に肉迫することもできないのだ。
拙著『ロシア革命100年の教訓』には、つぎのように書いておいた。
「「ユートピア」という言葉に注目すると、Utopiaは、ギリシャ語の否定辞 ού(ou, 無)とτόπος(topos, 場所)とを組み合わせた造語で、存在しない場所を意味している。同時に、εύ τόπος(eu topos)、すなわち「幸福な場所」、「楽園」という意味をあわせもっていた。重要なことは、テキスト自体はその国の存在を主張しているのだが、当の国の命名や作品の題はその存在を否定している点である。それどころか、その国を見てきた航海者ラファエル・ヒュトロダエウス(Hythlodaeus)の名前のなかに「法螺」「熟達した」という意味が含まれており、「法螺話の大家」くらいの意味が暗示されている。そう考えると、「ユートピア」を「空想」と訳したのでは、法螺話のおかしさやユーモアが抜け落ちてしまうように思われる。」
ここに、「空想」と「想像力」の差があるのだが、その話は拙著を参照してほしい。要するに、こうした分析にまで踏み込まなければ、ロシア革命の本質に迫ることはできないのである。
デザイン思考の陥穽
『週刊金曜日』の記事は紙幅が少なすぎるため、デザイン思考の陥穽について必ずしも十分な論考を加えていない。そこでもう少しこの点について、わたしの考察を陰で支えていただいている染谷武彦の指摘に全面的に依存しながら補足しておきたい。デザイン思考をソ連型社会主義に関連づけると、「設計主義(ここでいうデザイン思考)の論難の根拠は、一国の産業のあらゆる部面を事前に想定できるという思いこみにある。ソ連社会主義は、貨幣の廃絶を究極目標とした商品生産の廃棄を宣揚して国内経済の編成を執り行おうとした。だが、社会はそこに生起する森羅万象のあらゆる展開を事前に掌握できるものではない。商品生産を廃絶してすべてを計画化しようと突進したソ連社会主義ではあるが、膨大な人間社会の活動領域では、計画化によっては網羅しきれない広大な領域がある。ソ連経済の失敗は、貨幣経済の、商品経済の法則によるシグナルを利用しないでは社会的生産の編成は不可能であることを認めなかったことによる」(染谷)ということになる。
『週刊金曜日』の原稿では、1920年にソ連が人工中絶を自由化したことだけを紹介しておいた。キリスト教の世界では、受胎をコントロールすることは神の法に背くとして教会が反対の立場をとってきたわけだから、この決定はいわば、レーニンの指導するソ連共産党が「神」となった証であり、至高・究極のデザイン思考を示している。神に代わって、「神」とおぼしきレーニンが人工的に人間の数を管理しようというのだから。にもかかわらず、この事実はほとんど注目されていない。そこで、デザイン思考を批判する格好の標的として取り上げたわけだ。
全体主義を批判せよ
もう一人、塩川伸明が「1917年と1991年」という論稿を寄せているので批判しておきたい。この論文にも、「全体主義」という言葉が見当たらない。国家を政治と経済に分けて、「適当」に分析するだけでは、国家主権の恐ろしさを見過ごしてしまう(『週刊金曜日』の拙稿では、「全体主義を磁石のように引き寄せたのはロシア革命であった」と指摘しておいた)。和田も塩川もロシア革命に全体主義の影をみていない。こんな偏った分析しかできないのでは、「歴史に失礼」としか言いようがない。これでは、“Dishonest Abe”と同じ、不誠実・不正直な輩となってしまう。
塩川論文には、ロシア革命のもつ特殊性である「チェーカー」支配についても言及されていない。その結果、牽強付会なイデオロギー論を展開しているにすぎない。これでは、「ロシア革命100年の教訓」たりえないのである(拙著『ロシア革命100年の教訓』は歴史の風雪に耐えうるものであると自負している)。フランス革命などと比較しながら、「秘密警察」の誕生とその継続ないし頓挫まで踏み込んだ考察がなければ、ロシア革命の特殊性を抉り出すことはできないのだ。ついでながら、拙著『ネオKGB帝国』こそ、チェーカーや軍といった「合理的暴力装置」の側からいまのロシアを論じた画期的な書籍であると紹介しておきたい。
「私的領域」から「公的領域」へ
全体主義の問題を解くカギはハンナ・アーレントが教えてくれている。人間の歴史は私的領域の公的領域への浸食によって私的領域が全面化し、「社会」なるものが登場する過程をたどった。こう考えるアーレントにとって、この過程は、家長が一人支配(ワンマン・ルール)を行っていた時代から、社会における一種の無人支配(ノーマン・ルール)への変貌を意味している。各国によって異なるかにみえる歴史は、いわばこの「変奏」にすぎない。
全体主義は官僚による無人格の機構による無人支配であり、それは画一主義という没個性化により、「政治的なものと私的なものの古い領域はもとより、それ以後に樹立された親密さをも貪り食う傾向」をもつ。たとえば、人権問題を理由に、もはや各家庭内の活動でさえ、人権蹂躙として社会から制裁を受ける対象となりつつある。それは、社会という無人支配であるからこそ、可能な官僚による画一的な「行政サービス」の拡張でしかない。ただし、「社会」への無理解から、この社会は事実上、「国家」と同じであり、国家権力による私的領域への権力作用の拡大につながっている。
こうした傾向に弾みをつけたのがロシア革命である。貧困対策は部分的ながら成功したと評価してもよいが、それは国家権力の、つまり官僚による無人支配の拡大を招いてしまう。五木寛之の『さらばモスクワ愚連隊』を読めば、1960年代にはソ連にあこがれる日本人が大勢いたことがわかる。たしかにいい部分もあったのだ。帝国主義に対抗する論理を提示したことも、ないよりはよかったかもしれない。だが、長い歴史はロシア革命の本性隠すのではなく露わにするのに役立ったと言える。いまこの論考が示しているように、権威主義にすがるだけの連中を真正面から批判することが可能となったのだから。そして、なによりもデザイン思考の恐ろしさや全体主義への警鐘を鳴らしてくれたのだから。
歴史は繰り返す
皮肉なことに、歴史は繰り返す。「無頼」であったレーニンが「法の支配」(rule of law)を無視して革命を遂行する過程で、秩序化が必要になり、官僚支配を強めてしまう。それは、宗教の「国家宗教化」による変質とよく似ている。そこに、「法の支配」を優先させるだけの「凡庸な官僚」による無人支配がはびこるのである。ソ連は官僚国家であったことを忘れてはならない。なにしろ、公務員がはびこる国家だったのだから。
600万人とも言われるユダヤ人虐殺に手を染めたのが凡庸な官僚であったことを想起しよう。具体的には、アルゼンチンに逃亡中、イスラエルの諜報機関によって逮捕された後、人道(人類)への罪などで有罪となり1962年に絞首刑となったアドルフ・アイヒマンを取り上げてみよう。彼は親衛隊の情報部ユダヤ人担当課に属していた「官僚」であり、ドイツの法に従ってユダヤ人の収容所送りという「命令」を執行しただけであったと主張した。いわば、事務処理をこなす官僚が数百万人を死に至らしめたことになる。ゆえに、アーレントはこのアイヒマンの悪を「悪の陳腐さ(凡庸さ)」(banality of evil)と呼んでいる。法の遵守のもとで思考停止してしまう凡庸な官僚であれば、だれしもが同じ罠にかかり、他人の生命をまったく平然と奪うことに加担できるのだ。
そしていま、“Dishonest Abe”として世界中から嘲笑されている安倍晋三は「法の支配」をさかんに説く。「法の支配」や法律遵守を隠れ蓑にしながら、まったく不誠実な答弁しかしない官僚を看過し、昇進までさせている。こうした現実の事態も、実はロシア革命が引き寄せた全体主義的傾向の一環と断じることができる。
官僚だけではない。国民も同じだ。「法律に反しなければ、なにをしてもいい」かのような生き方を真っ当と考える連中が多すぎる。コンプライアンス(法律遵守)を声高に叫ぶだけでは本当はなにも解決しないのである。「法の支配」を超える「倫理」とどう向き合うべきかという疑問に真正面から取り組まないかぎり、「統治」の問題を解決へと導くことはできないのだ。この点をしっかりと理解できている人が少ないから、Dishonest Abeに騙されるのだ。
いま若者は目先の就職のために、アベノミクスを支持し、老人は株価上昇に目がくらんでいるようにみえる。そこには、将来の人類という、「法の支配」のおよばない人々への視線はない。ゆえに、財政破綻の悪夢を先延ばしする日本の経済政策の愚行を断罪することさえできないでいる。わたしは、近く、『クレプトクラートを成敗せよ』(仮題)という本で、財政破綻を引き起こすための「金融テロ」を具体的に紹介しようともくろんでいる。もちろん、そんな事態になってほしくないための警鐘を鳴らすためだが、こうした警告をまじめに発しなければならないほど、事態は切迫しているのだ。
困り果てる権威主義
繰り返しになるが、『現代思想』のような「インチキ権威主義に気をつけて」と強調しなければならない。昔であれば、和田春樹や塩川伸明といった東大教授がなにか言えば、その権威にたてつく者がいても、その意見を表明する場がなかった。その結果、権威者の無能は隠蔽され、権威を保つことが可能であった。だが、いまはこうして彼らに対して疑問符をつきつけることができる。もしわたしが編集者であれば、こんな連中に話を聞いたり、原稿を書かせたりしないだろう。意味がないからである。過去に間違え、それを反省しているとは思えない人物から得るものはない。要するに、“Dishonest”なのである。
ほぼ同年代の柄谷行人とこの特集に登場する「知識人」・「専門家」を比べてみよ。前者の業績は歴史に耐えるに十分だが、後者はその権威がなくなればあっという間に消え去るだけだろう。なぜなら後者の研究がとるにたらないものであったことは歴史が証明してくれるからだ。その決定的な差こそ、「国家」に対する考察の深さの差にある。あるいは、ここで紹介したアーレントのような深い洞察力の欠如は権威主義の時代においては隠蔽できるかもしれないが、いまの時代は権威にすがって無能を隠そうとしても、かれらの無能は暴き出されてしまう。わたしのような「無頼」こそ、こうした権威主義者の馬脚を照らし出さなければならないと思っている。いわば、「21世紀龍馬」の仕事だ。
全体主義の恐怖が世界的に広がっているいまだからこそ、ロシア革命100年を機に、「全体主義を撃つ」ことが求められている。しかし、権威主義のもとでその無能を糊塗してきた連中に頼っていては、全体主義の足音さえ聞きとれない。これは大変に残念な事実である。
「目的の正しさ」不在の意味
全体主義の恐ろしさをロシア革命は教えてくれた。神に代わってレーニンが登場し、そのレーニンに代わってスターリンが現れる。1953年3月に死んだスターリンも1961年までの8年間、人形のようなレーニンと並んで、レーニン廟に安置されていた事実は重い。ここで思い出すべきなのは、「ケノーシス」である。これは、「服従」(隷従)によって「救済」されるという「ケノーシス」という観念だ。詳しくは拙著『ロシア革命100年の教訓』で書いたことだが、ここでわかりやすく再論しよう。
正教(Orthodoxy)では、父なる神と子なるキリストと聖霊(三位)が神をなす。聖霊は神と人間を繋ぐ媒体で、聖霊によってイエスは処女マリアの身中に宿ったとされている。その聖霊は正教では「父」から生じるとされているから、三位のうち、父、子、聖霊の位階が明確なのだが、ロシア人は人間のかたちをしたキリストに強い親近感をもつ。人間キリストへの尋常ではない服従は、皇帝や絶対的指導者たるスターリンへの隷従精神に通じるものがある。これこそ、ロシア的人間のもつケノーシス気質と言えるかもしれない。このとき注目されるのは、ケノーシスの意味する救済が贖罪や悔い改めを媒介せずに可能だということだ。そう考えると、神からやってくるはずの救済が人間によって簒奪される可能性があることになる。それは、神への服従ではなく、レーニンやスターリンに隷属することで救済につながる可能性を排除しないことにもなる。
こうしてレーニンやスターリンが神として降臨するのだ。このとき、心に浮かぶのは、ヴァルター・ベンヤミンの鋭い指摘である。彼は、「暴力批判論」のなかで、「正しい目的は適法の手段によって達成されうるし、適法の手段は正しい目的に向けて適用されうる」というドグマをめぐって、「手段の適法性と目的の正しさについて決定をくだすものは、決して理性ではない」と指摘、「前者については運命的な暴力であり、後者については――しかし――神である」と述べている。「目的の正しさ」を決定する「神」がいなくなると、もう「正しさ」自体に真摯に向かい合うことがなくなってしまうのだ。
これこそ決定的に重要な言説である。ここでデザイン思考と呼んだ設計主義思想はヨーロッパではアリストテレスの目的論と合わせる形で長く受容されてきたことを想起しなければならない。この目的論は物質が自ら運動するとみる自然哲学を否定する見方を端緒としている。物質の自己運動を否定すると、運動を引き起こす淵源としてなにかを想定せざるをえなくなるから、たとえばプラトンは神を想定した。アリストテレスはプラトンと異なり、物質の自己運動性を認めたが、その運動(生成)は物質に内在する原因によって生じると考えた。その原因は、質量因と始動因、目的因と外相因であるとしたうえで、運動が目的(終り)をもつと考えた。それが目的因のことである。ただし、この見方は事物が生成したのちに初めて見出されるものであり、事後的観点から説明するという姿勢を意味している。事後の勝者が自らに有利な歴史を捏造できることになる。
ロシア革命で誕生したソ連は人間のデザイン思考ないし目的論的アプローチを全面的に取り入れていた。この事実を知ったうえで、前記のベンヤミンの言説を考慮すると、目的論的アプローチがめざす「目的の正しさ」を保証する「神」がいなくなると、その正しさはなにものも保証できなくなることを意味している。それでは、デザイン思考や目的論的アプローチができなくなるから、「神」としてのレーニンやスターリンが登場せざるをえなかったというわけだ。
この原理こそ全体主義にもあてはまる構図ということになる。要は、無人支配(ノーマン・ルール)という官僚による全体主義的支配は「目的の正しさ」を見失った「神」なき近代化後の人類につきつけられた課題なのである。通常、この事実は主権国家によって義務教育を通じて隠蔽されている。ゆえに、ここで書いたような事実に気づいている人はほとんどいない。それは、「正」という漢字の本来の由来を知っている人がほとんどいないと同じだ。
ここで、閑話休題11「“Dishonest Abe”から“Hitler Abe”へ:バカばかりの官僚・マスコミ」で指摘したつぎの文章を思い出してほしい。
「白川静著『字統』(p. 510)によれば、「正」は「一」(城郭で囲まれた邑)と「止」(足跡の形)を組み合わせた言葉であり、「都邑に向かって進撃する」という意味をもち、都邑を征服することにつながっている。「正」が多義化するにおよんで「征」がつくられる。「正」はもと征服を意味し、その征服した人々から貢納を徴収することを「征」と表すようになる。忘れてならないのは、重圧を加えてその義務負担を強制することを「政」ということだ。そして、そのような行為を「正当」とし、「正義」とするに至るのだ。ゆえに、本来、征服支配こそ、強者の正義であったのである。
このような経緯を知っていれば、「正しさ」なるものが強者の押しつけでしかないことがわかるだろう。「神」がいればまだしも、「神」がいなくなると、「神」たらんとする「国家」が勝手な「正しさ」を押しつけ、事態がますます悪くなっているのだ。
どうか、よく学んで、「正しさ」についてよく考えて、『現代思想』の押しつけるような、権威主義に基づく似非学者のバカげた考えに騙されないようにしてほしい。心からそう願っている。




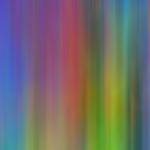




最近のコメント