カント生誕300年を迎えて想うこと
2024年4月22日は、イマヌエル・カントの生誕300年にあたる。この日に合わせて、ここではまず、私がカントに言及したことを振り返ってみたい。そのうえで、いまのカント理解について書いておきたい。
『ロシア革命100年の教訓』
拙著『ロシア革命100年の教訓』のなかで、私は、ロシア革命の混乱期の1920~21年にかけて書かれたエフゲーニィ・ザミャーチン著『われら』について論じた(Замятин, 1920-21=1992)。本国では発行できず、1924年にチェコの雑誌にロシア語原文が発表された(英語版は1924年に刊行)。これを契機に、ソ連当局への公然たる挑戦とされて、ザミャーチンは反革命家の烙印を押され、1931年にパリに出国、1937年3月にパリで死亡した。『ドクトル・ジヴァゴ』と同じように、ミハイル・ゴルバチョフのペレストロイカ後、1989年以降、この作品を収めた数多くの単行本が刊行されるようになった。
ここで、私が書いたことを少しだけ引用してみよう。
****************************************
『われら』は、200年戦争を経て1000年前に全地球を征服して単一国の支配下においたころ、すなわち、1200年ほど先の世界国家「単一国」を舞台に、そこの数学者で宇宙船「インテグラル」の製作担当技師である「D-503号」の手記という形式で語られる。彼が同国への叛乱に巻き込まれていく話ということになる。
『われら』を翻訳した川端香男里の解説によれば、「長年にわたる教育と、守護者と呼ばれる秘密警察の監視のもとで、個性と自由が除去された未来都市」が描かれ、そこでは、「人々の行動は時間律法表によって画一化され、愛情、生殖も国家の統制下にある」。人々は員数(ナンバー)として扱われ、男性は子音、女性は母音で表わされる(「D-503号」は「D」だから男性ということになる)。自然の野蛮な力は「緑の壁」でさえぎられ、動物も植物もすべて取り除かれている。建物はすべてガラスで、守護者が国民生活のあらゆる部分を監視することができる。
愛と自由への攻撃と満場一致
具体的には、朝7時、われら何百万人が一人のように起床する。「同一時刻に百万が一つになって仕事をはじめ、百万が一つになって終える。百万の手を持てる一つの身体(からだ)となって、律法表に指示通り同一秒にスプーンを口へと運び、同一秒に散歩へ出かけ、講堂に行き、テーラー訓練場へ行き、眠りにつく」(Замятин, 1920-21=1992, p. 21)。「愛」は攻撃され、300年ほど前に性(レクス)規制法(・セクスアリス)が布告されて、員数(ナン)成員(バー)のすべてが性的所産として任意の員数成員に対する権利をもつことになり、各自に適合したセックス・デー予定表が作成され、申請書を書いて自分のセックス・デーにこれこれの員数成員を利用いたしたく云々と願い出て適当なクーポン綴りを受理する。個人時間である16時から17時と、21時から22時に、部屋のブラインドを降ろしてクーポンを行使するのだ。
「自由」も攻撃の対象となっている。自由と犯罪が切り離しがたく結びついているとして、人間の自由をゼロとすることで人間を犯罪から救い出す。
毎年一度、「満場一致デー」が開催される。員数成員に恩恵を施す人である「恩人」に賛成の挙手をする日なのだ。だが、数千の手が「反対」の挙手をする事件が起きる。しかし、「彼らの投票を計算に入れることは無意味なこと」とされ、「幸福の敵」は処罰の対象となる(Замятин, 1920-21=1992, p. 225)。
この出来事に対して、菊池理夫はつぎのように書いている(菊池, 2013, p. 355)。
「ここでとくに問題にしたいのは、圧倒的多数の者がこの体制のもとで平和に、安全に「幸福」に暮らし(もちろん、そう思い込まされているとしても)、それゆえに「恩人」に賛同していることである。つまり、これはまさに「全体主義的民主主義」の危険性を指摘していると理解できる点である」。
これは、ソ連においてすでに広がりつつあった全体主義的傾向への厳しい批判を含んでいたことになる。
「緑の壁」の内と外
『われら』はたんに全体主義国家ソ連を批判するだけでなく、科学技術を信奉することへの警句を含んでいることに留意しなければならない。「緑の壁」の内側には動物も植物も除外されていたが、壁の向こうで生き残った人々がいたのである。
「裸のまま、森の中へはいって行ったの。そこで、木木や、けものたち、鳥たち、花、そして太陽から学んだの。彼らは一面毛に覆われることになったけれど、この毛の下で温かい血を守ることができたのよ。あなたたちの場合はもっと悪くなってるわ。身体中数字だらけとなって、数字が身体の上をしらみのように這い回っている」(Замятин, 1920-21=1992, p. 251)。
これは、「D-503号」の愛した「I-330号」が「D-503号」に話して聞かせた内容である。「身体中数字だらけとなって、数字が身体の上をしらみのように這い回っている」のは、現代のわれわれ自身にもあてはまるのではないか。そう考えると、ザミャ―チンの批判は全体主義国家ソ連だけを射程としたものではなかったと指摘しなければなるまい。
想像力摘出手術
叛乱という事件に対して、単一国は員数成員に想像力摘出手術を強制する措置をとる。機械装置には想像力がない。想像力という病気を治療するには、幸福への道をさえぎる最後のバリケードである想像力というバリケードを爆破させればいい。単一国の科学の最新の発見によって、想像力中枢の存在が明らかになったから、脳神経節の「X線による3回の焼灼を受ければ、諸君は想像力病を治癒し得るのである」というのだ(Замятин, 1920-21=1992, p. 272)。これを前提にして、「恩人」が「D-503号」に話した内容を読むと、そこにはキリスト教への容赦のない批判がある。
「キリスト教の最も慈愛心にみちた神ですら、すべての服従せぬやからをゆっくりと地獄の火で焼いている――彼も死刑執行人ではないのかね? それにキリスト教徒によって火刑にされた人数は、火刑にされたキリスト教徒の人数より少なかったのだろうか? それにもかかわらず――いいかね――それにもかかわらず、この神が愛の神として長年の間、讃えられていたのだ。不条理かね? いや、その反対だ。根絶やしにすることのできない人間の良識への、血で書かれた特許状だ」(Замятин, 1920-21=1992, p. 326)。
「古代の天国についての夢想……思い出してみたまえ。天国ではもう願望も、憐れみも、愛も知らない――それには想像力の手術を受けた至福の人(手術を受けて初めて至福を得るわけだ)と、それに神の奴隷である天使がいる」(同, p. 327)。
想像力が神や天国を人間にもたらしたのであれば、この想像力を取り除くことで、愛も憐れみもいらない至福に出会えるというのである。
ここではっきりと意識しなければならないのは、想像力(imagination)と空想(fancy)との違いである。想像力は従来、知覚の疑似的な再現能力、あるいは恣意的な空想能力として低くみられていた(Karatani, 2014, p. 216)。イマヌエル・カントこそ、感性と知性を媒介するものとして、また、知性に先立つ創造的能力として想像力を初めて見出したのである。想像力は恣意的な空想とは異なるのだ(柄谷, 2010, p. 323)。このため、想像力の摘出は知性にも影響をおよぼし、単一国の科学にも打撃をおよぼすことになるだろう。
****************************************
長い引用を紹介したのは、こうでもしないと理解してもらえないのではないかと思ったからである。このとき私が強く意識していたのは、科学と知性、知性と感性の問題であった。
別の引用
『ロシア革命100年の教訓』にある、別のところに登場するカントへの言及をみてみよう。これも、私の思想を理解してもらうために、長めに引用してみよう。
****************************************
ハイエクのいう「自生的秩序」
ハイエクは構築主義者の合理主義(constructivist rationalism)の誤謬を批判している。その誤謬はデカルトの二元論に密接に関連しているとして、その一方に、自然の宇宙の外に独立して存在する精神の実体という概念をおき、はじめからこうした精神を授けられた人間が生活する社会や文化の制度をデザインすることを可能にしてきたとみなしていたと、ハイエクは指摘している(Hayek, 1973, p. 17)。なお、構築主義(constructivism)とは、なにが「現実」として見えるのかはその生物学的有機体に備わった固有の器官の働きによって決定されるという立場を意味している(千田, 2001, p. 14)。Constructionismにおいて焦点とされるのは、人々が経験を「語りなおす」のかという、意味の共同的な達成過程である。
ハイエクは構築主義者の合理主義と(内的展開する)合理主義を区別している。それは抽象性に対する考え方の違いによる。前者の特性は、抽象的概念が精神によって十分に精通できない具体物の複雑性を処理するための手段であると認めないことにある。他方、後者は、十分に理解できない現実性を処理することを可能にする精神にとっての不可欠の手段として抽象性を認めている。わかりやすく言えば、抽象性を軽視して実体を重視することで社会や文化の制度をデザインしようとするところに構築主義者の合理主義の特徴がある。具体的には、全体主義、社会主義、共産主義、さらにケインズ的な近代経済学もこうした構築主義者の合理主義だとして批判されている。
さらに、ハイエクは「秩序」について考察し、構築主義的な秩序に関連する「つくられる秩序」(made orders)と「自生的秩序」(spontaneous orders)を区別して、後者の重要性を強調している。これはギリシャ哲学の影響を受けている。ハイエクによれば、ギリシャ人は秩序についてかけ離れた二つの言葉をもっていたという(Hayek, 1973, p. 37)。具体的には戦闘における秩序(軍の編成単位)のような「つくられる秩序」を表わす「タクシス」(taxis)と、国家ないし共同体における「正しい秩序」を表わす「コスモス」(kosmos)だ。つくられる秩序ないしタクシスは外因的でシンプルで具体的なものであり、つくり手の目的に仕えるという特徴がある。これに対して、自生的秩序ないしコスモスはこうした特徴をもたず、目的をもたない。つまり、自生的秩序を重視するハイエクは目的論的な立場をとらない。
マンデヴィル、ヒューム、スミスの思想
ハイエクは自生的秩序の理論的基礎はバーナード・マンデヴィルによってもたらされたと考えている。ついで、道徳的ルールや社会制度の合理主義的説明に一撃を加えた思想家として、ハイエクはデイヴィッド・ヒュームやアダム・スミスを評価している。ここでは、ハイエクの評価が必ずしも的を射ていない事実をのべているクリスティナ・ペトソウラスの主張(Petsoulas, 2001)を紹介しながら、ハイエクの見解を批判的に解説したい。
ハイエクは、マンデヴィルがその著書『蜂の寓話』によって「秩序だった社会構造、たとえば、法や道徳、言語、市場、貨幣といったものの自生的成長や技術知識の成長の古典的なパラダイムのすべてを発展させた」と褒めている(Hayek, 1978, p. 253)。ハイエクは、ヒュームの考えが人間の理解の狭い限界についての懐疑的見方に結びついており、ヒュームの出発点が道徳への反合理主義者的理論にあると主張している(同, pp. 110-111)。さらに、スミスについては、「予想可能な目的のための計画的なデザインの産物としてすべての制度を解釈してきた、初期の無邪気な構築主義者の合理主義に、意識的理性の効果的な利用の条件や限界を吟味する、決定的に重要な内的展開する合理主義を取って代えた」点を評価している(同, pp. 71-72)。
しかしペトソウラスによれば、こうしたハイエクの主張は彼の曲解に基づいており、必ずしも肯定できない。彼女は、「ハイエクの自生的秩序理論は人間のデザインのないなかで社会秩序がどのようにもたらされるかの「科学的な」説明を提供している」としたうえで、ハイエクがつぎの二つのタイプの説明を結合していると記述している(Petsoulas, 2001, p. 186)。
①「不可視の手」という説明:「不可視の手」に応じて、市場秩序はデザインないし集団的合意によってもたらされるのではなく、多くの個人が別々に彼らの目標を追求する行為の意図せぬ結果としてもたらされる。
②社会秩序の自生的形成メカニズムを提供するルールの文化進化理論:文化的進化は人間理性とは独立して起きる過程であり、ルールはルールの機能を個々人が理解しているために選択されるのではない。むしろ、最初に他の理由で採用されたか、あるいはまったくの偶然に採用された実践が保持されたのは、それらを採用した集団がそのルールを他者に広げることを可能にしたからにすぎない。
ハイエクはこの二つのタイプの説明を明確に区別せずに混同しながら自説を展開していることになる。ただ、マンデヴィルもヒュームもスミスも②の文化進化論の立場をとっていないと、ペトソウラスは指摘する。彼らは、試行錯誤(トライ・アンド・エラー)の理論を支持し、意識的実験が文化において支配的であるとの見方をとっている。とくに、ヒュームとスミスはルールの選択を個人の志向性とルールのもたらす便益理解に帰しているのであって、ルールが人間の理解を超えているとするハイエクの立場とはまったく異なっている。ハイエクは正義のルールが思いがけない「突然変異」として出現するかのようにみなしていることになる。だが、そこまで主張するのは明らかに行き過ぎだろう。
バランスの問題
試行錯誤は人間の意志によって意図的に試されるものである。ただし、模倣(ミメーシス)によって主たる文化が形成されてきた以上、そこに人間の意志がある程度までは反映されていることになる。とはいえ、人間にかかわるさまざまのルールが突然変異によって唐突に生まれるというのはおかしい。過去の歴史のうえに、新たなページが加えられることで未来は築かれるのであり、いきなり別のルールが出現してルールとして支配的になるわけではない。
ハイエク流に言えば、「つくられる秩序」ないし「タクシス」と「自生的秩序」ないし「コスモス」という二つの秩序のバランスが大切なのであり、「つくられる秩序」ないし「タクシス」を過度に重視すると、国家が全面的に国民を支配することで秩序を維持しようとする全体主義国家の到来につながりかねない。
もう一つ重要なのは、ハイエクが目的論を否定する立場にあったことである。自生的秩序は目的をもたない。すでに紹介したサイモンが主張するように、人間は限界合理性(bounded rationality)しかもたないであれば、その合理性の限界をわきまえることが必要なのであり、なにか目的や目標を定めて行動するにしても、それは試行錯誤を最初から前提にしたようなものであり、少し試してみてまた再試行するものでしかない。いやむしろ、将来の変更や選択の余地を残したものとして繰り返しトライするという積極的な姿勢が求められる。
もちろん、制度はいったん変更すると、元に戻すのは難しい。新しい制度の効果を判定するにも一定の時間が必要になる。それでも、究極の目的や目標があるかのように考えて、ある種のルールや制度を絶対的に押しつけるのではなく、柔軟にしなやかに対応することが優先されるべきであるという思考こそ大切なのではないか。ゆえに、筆者は拙著『官僚の世界史』のなかで、「ぎすぎすした関係」から「なめらかな関係」への移行を主張する鈴木健の主張に賛意を表したのである(鈴木, 2013)。
この原稿を書き進める途上で、熊野純彦著『カント 美と倫理とのはざまで』を読む機会があった。そこに書かれているのは、『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』を通じてカントが構築した思想である。「要するに、カントの批判哲学とは、自然神学をすでに廃墟とみて、その断念にうえに築かれた思考であったのである」という指摘からわかるように、カントの目的論にかかわる考察を徹底的に解説している(熊野, 2017, p. 296)。
筆者が強調したいのは、カントが目的論を断罪したわけではないという点である。あくまで目的論を徹底して問う姿勢を貫いたのだ。その意味で、ハイエクのように安易に目的論を否定することはできない。むしろ、大切なのは目的論を疑うことであり、デザイン思考に抗う姿勢にある。そこに、内的展開たるエヴォリューションが生じるのだ。
****************************************
さらに、『ロシア革命100年の教訓』には、つぎのようなカントにかかわる記述がある。
****************************************
官僚の思考停止
つぎに、「なにも考えないでただ執行する」ことを旨とする官僚について考えたい。この問題の深刻さを理解するには、600万人とも言われるユダヤ人虐殺に手を染めたのが凡庸な官僚であったことを想起するところからはじめるのがよい。具体的には、アルゼンチンに逃亡中、イスラエルの諜報機関によって逮捕された後、人道(人類)への罪などで有罪となり1962年に絞首刑となったアドルフ・アイヒマンを取り上げてみよう。彼は親衛隊の情報部ユダヤ人担当課に属していた「官僚」であり、ドイツの法に従ってユダヤ人の収容所送りという「命令」を執行しただけであったと主張した。いわば、事務処理をこなす官僚が数百万人を死に至らしめたことになる。ゆえに、アーレントはこのアイヒマンの悪を「悪の陳腐さ(凡庸さ)」(banality of evil)と呼んでいる。法の遵守のもとで思考停止してしまう凡庸な官僚であれば、だれしもが同じ罠にかかり、他人の生命をまったく平然と奪うことに加担できるのだ。
問題は、法を遵守するだけでその執行を思考停止状態で行う官僚がいまでもあちこちにいるという現実である。アイヒマンと同じ論理で平然と権力をふるう官僚が存在する。しかも、官僚がもつエリート意識が断固とした権力行使を行わせることになる。
凡庸な官僚が同じ過ちを繰り返さないようにするにはどうしたらよいのか。その答えは簡単ではない。アーレント自身は、「法を守るということは、たんに法に従うということだけでなく、自分自身が自分の従う法の立法者であるかのように行動することを意味するという」、ドイツでごく一般的に見られる観念に同調しているようにみえる。これは、法の背後にある原則や法が生じてくる源泉へと自分の意志を同化させなければならないというアーレントの主張とどう関係するのか(伊藤, 2003, p. 19)。官僚が遵法精神をもとに行動するのであれば、いかなる法であっても思考を停止して執行するだけでいいのか。
この問題は究極的にはカントの主張に帰着する。合法も違法も、「義務を果たす/果たさない」という同一の領域に属するだけであり、倫理は、この領域には収まりきれないのだ。「倫理は、法やその違反といった枠組みには収まらない」ことから出発しなければならないのである(Zupančič, 2000=2003, p. 27)。それは、「義務が課されていた以上、それに従って行動しただけだ」という官僚的言い訳にどう立ち向かうかを問うものとみなせる。しかも、こうした言い訳は官僚という職業をもつ者だけでなく、現代を生きる大多数の者にとっての言い訳になっている。
****************************************
道徳的義務
私がカントについて勉強しなければならなかったのは、2003年に刊行した『ビジネス・エシックス』の執筆途上で道徳について考察する必要があったからである。フリードリヒ・ニーチェについて考えたのも、このことであった。
この延長線上に拙著『復讐としてのウクライナ戦争』がある。何しろ、ニーチェは、弱者のもつ「憎悪、嫉妬、猜忌、邪推、宿怨、復讐」といった「ルサンチマン」(ressentiment)の精神を取り鎮める手段として、「能動的な、攻撃的で侵略的な人間」が、「ルサンチマンの対象を復讐の手から奪い去ったり、ときには復讐の代わりに平和と秩序にたいする闘争をやらせたり、またときには妥協を考えだしたり提議したり、場合によってはこれを強要したり、ときには損害を補償すべき一定の等価物を規範にまで高めて、爾後ルサンチマンをしていやでもこれを基準にその損害を補償させたりする」ことを繰り返してきたと説いているからだ(括弧内は『ニーチェ全集11 善悪の彼岸 道徳の系譜』449~450頁)。
カントについては、刑罰論の部分だけの取り上げた。せっかくだから、引用してみよう。
****************************************
復讐の法制史
ここで、カイウス・トゥオリ(Kaius Tuori)著「法と合理性: 初期法人類学における動機と人間の代理性の理解に関する歴史的考察」(https://journals.openedition.org/cliothemis/pdf/611)を参考にしながら、復讐規制と法の発展をめぐる法制史について説明したい。
トゥオリは、「復讐は伝統的に学者や道徳理論家によって、正義の逆転、文明の進歩とともに廃止される原始的衝動とみなされていた」と指摘する。血の復讐のような復讐は、文明のゆっくりとした進歩によって、まず紛争を解決するための形態としての暴力が制限され、最終的には根絶されるみされるようになる。これらの理論における最初の論点は、「ほぼ常に、暴力的衝動を制御できない野蛮人、あるいは社会が彼を制御できないという図式であった」とのべている。
「文明」(civilization)という概念は、18世紀後半以降、ヨーロッパの思想界で広がるようになる。1767年、アダム・ファーガスンは『市民社会史論』のなかで、「文明」と「野蛮」の概念を対比させて広く使われるようになる。とすれば、復讐への厳しい規制という視線は18世紀後半以降、広範に広がっていたことになる。ただし、そうした見方が広がる前から、復讐に対する道徳的非難は存在した。たとえば、フランシス・ベーコンは1625年、「復讐について」(https://people.brandeis.edu/~teuber/bacon.html)において、「復讐は一種の野生の正義であり、人間の本性がますます正義を重んずるようになればなるほど、法は復讐を排除すべきである」と明確に語っている。
つぎに、刑罰と復讐との関係を考えるうえで、大きな影響力をおよぼした五人の見解をまとめてみた。
- カント
18世紀後半になって、イマニュエル・カントは『道徳形而上学の基礎づけ』のなかで、「刑罰権」を取り上げている(ここでは、松井富美男著「カントの正義論」[https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/ja/list/creator/de3d51da628be5e3520e17560c007669/item/17341]と北尾宏之著「カントの刑罰論」[http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/625/625pdf/kitao.pdf]を参照)。「命令権者が[法の]服従者に対して、その服従者が罪を犯したがゆえに、彼に対して苦痛を科す権利」とされている。命令権者は法の執行権者であり、服従者とは法に従い、法の保護を受ける「臣民」としての人間だ。ここでの議論は、自然状態ではなく、すでに公法、国家法が存在している法的状態を前提としており、いわゆる公的犯罪だけが問題にされていることになる。これは、刑事裁判の対象であり、手形の偽造、窃盗、強盗などを含めている。これとは別に、民事裁判の対象となる私的犯罪があり、このなかには、詐欺や横領が含まれているとされる。
カントは、 裁判による刑罰、すなわち、公的犯罪への刑罰が「犯罪者や市民社会のための善を促進する手段としてのみ科されるのはなく、罪を犯したという理由だけで犯罪者に科されなければならない」という立場にたっている。そして、「私は同害報復(ius talionis)を形式の上から相変わらず刑罰原理としてアプリオリに規定する唯一の理念とみなす」とのべている。この立場は、他の目的のための手段として刑罰を科すべきだとする目的刑論と対立する。
カントは、「公的正義がその原理と規準にする刑罰はどのようなもので、どの程度のものか。それは一方の側よりも他方の側に傾かない(正義の天秤の針が示す)均等(Gleichheit)の原理である」と指摘している。まさに、カントは最初に紹介した均等性に正義を見出してきた人類の歴史に沿う立場にたっていることになる。
ただし、カントの応報主義的立場は被害者本人による復讐自体を肯定しているわけではない。なぜなら、公的犯罪において、刑罰執行権をもつのは国家であるからだ。カントは、国家は個人の外的自由を保障する代わりに、個人は国家の命令(法)に服従する、といった「根源的契約」を国家との間に結んでおり、そのために国家は契約違反者としての犯罪者を罰することができる、というのだ。前述したように、カントが問題にしているのは、公法違反という公的犯罪であり、「単に一個人が危機に瀕するのはなく公共体が危機に瀕する」ような違反であり、ゆえに、公共体が刑罰を科すことになる。それは被害者の復讐感情に基づくものではなく、正義に基づく刑罰なのだ。
ただし、私の見方では、その公的刑罰そのものは、キリスト教の「罪というものを贖う(罪滅ぼしをする)ことではじめて神の報復を避けられるとする信念」をもとにしているために、復讐心自体を否定していない、と指摘しておきたい。ゆえに刑罰の制度が進んでも、復讐心自体は個人のレベルでは意識的に、集団のレベルでは無意識的に息づいたままなのである。
****************************************
いま考えるカント
このようにみてくると、私自身にとって、カントは全体的な視角をもたらしてくれる「羅針盤」のような存在であるような気がしている。最後に、いま現在の私が気にかけているカントの言説について書いておきたい。また例によってメモ書き代わりに書き留めておくものだ。ここでの参考文献は、スタンフォード大学のサイトにあるカントに関する概説だ。
よく知られているように、カント最大の功績は、人間の理性の成果としての科学を救出したことだろう。それをごくわかりやすく書いたのが拙著『サイバー空間における覇権争奪』に書いたつぎの記述である。
「神の名のもとに何もかもを説明する、すなわち、完全なものたるアイディールから繙くという思考法が大きく揺らぐ事件は1755年11月1日(諸聖人の日[万聖節])に起きたリスボン大地震である。5万人以上が死亡した地震と津波がカトリック教徒を襲ったことで、神によって人間の力の及ばない自然の猛威を説明することに対する疑問が広がったのだ。天変地異に神の正義をみるのではなく、自然そのもののメカニズムにその原因をみようとする科学的思考が広がるきっかけになったと考えられている。それを実践したのが哲学者エマニエル・カントであり、かれはこの地震をめぐる書物さえ書いた。興味深いのは、この地震と津波が人間の安全保障に対する問題を喚起し、これを神の正義の問題ではなく人間の問題としてみる視線を養ったことである。」
この点をもう少し哲学的に説明してみよう。The Ethics of Beliefでは、つぎのように説明されている。
「イマヌエル・カントにとって、十分な理論的証拠がない場合に信念(あるいは信仰)を正当化することができる考慮事項は、一般的に(専らではないが)道徳的なものである。たとえば、ある命題p(たとえば、人間の意志は非両立論的に自由であるという命題)に対して、一方にせよ他方にせよ十分な証拠がなく、pの真理に立つことを要求する道徳的な目的を設定し、自分が持っている証拠がpの真理の方向を指し示している場合、人はpを真とすることが許される(時には要求されることさえある)。この「真とすること」(ドイツ語では「Fürwahrhalten」)は、「理論的」な根拠ではなく「道徳的」な根拠に基づいて正当化され、「知識」(Wissen)ではなく「信念」(Glaube)や「受容」(Annehmung)として数えられる(Kant 1781/1787, Chignell 2007)。」
『純粋理性批判』は、ニュートン科学の登場で、啓蒙主義の誇りであり、人間の理性の力に対する楽観主義の源であった近代科学が、自由な理性的思考が支持すると期待されていた伝統的な道徳的・宗教的信念を弱体化させる恐れがあった時代において、科学も道徳的・宗教的信念もともに救出する根拠を基礎づけたことで知られている。別言すると、理性自身による理性批判が、伝統的な権威に助けられることなく、抑制されることなく、ニュートン科学と伝統的な道徳と宗教の両方に確実で一貫した基礎を確立することを示すことに成功したのだ。
よく知られているように、カントはそのために、科学を外観の領域に限定し、超越的形而上学、すなわち、人間の可能な経験を超越する事物それ自体についての先験的知識は不可能であることを暗示している。わかりやすくいえば、「神、自由、不死に対する信念は、厳密に道徳的な根拠をもつものであり、道徳的な根拠に基づいてこれらの信念を採用することは、それが誤りであることを知ることができれば、正当化されないからである」ということになる。カント自身、「信仰の余地をつくるために、私は知識を否定しなければならなかった」とのべている。「知識を外見に限定し、神と魂をそれ自体では知りえない領域に追いやることで、神や魂の自由や不死に関する主張を反証することが不可能になり、道徳的な議論によって信じることが正当化されることになる」。
この点については、拙著『サイバー空間における覇権争奪』の注において、つぎのように書いておいた。
「カントは「物自体」(Ding an sich)と現象(Ersheinung)を区別することで、後者については人間理性が創造者たりえることを示した。つまり、人間理性が見るものは、物それ自体においてある姿ではなく、物のわれわれにとっての現われでしかないというわけだ。人間理性は少なくとも現象界を存在せしめ、それに合理的構造を与える「超越論的」(transzendental)主観ということになり、神的理性の後見なしにそれでありうることになった。」
理論哲学は、われわれの知識が厳密に制限されている外見を扱い、実践哲学は物事それ自体を扱うが、それは物事それ自体についての知識をわれわれに与えるのではなく、実践的な目的のために、物事に関する特定の信念の合理的な正当性を提供するだけである。
カントによれば、人間の理性は必然的に魂、世界全体、神についての観念を生み出す。そしてこれらの観念は、それらに対応する超越的な対象についての先験的知識をもっているかのような錯覚を不可避的に生み出す。しかし、これは幻想だ。「実際には私たちはそのような超越的な対象について先験的な知識をもつことはできないからである」。にもかかわらず、カントはこれらの幻想的な観念が積極的で実際的な用途をもつことを示そうとする。こうしてカントは、道徳の形而上学と呼ぶ実践的な科学として再構築する。カントの見解では、魂、世界全体、神についての我々の観念は、それぞれ人間の不死、人間の自由、神の存在についての道徳的に正当化された信念の内容を提供するが、それらは思弁的知識の適切な対象ではないという。
「自由」という概念
こう理解することで、はじめて、物事それ自体を扱う実践哲学における「自由」が問題となる。物事それ自体に関するもっとも重要な信念は、人間の自由に関するものである。自由が重要なのは、カントの考えでは、道徳的評価は、そうでないことをする能力があるという意味で、人間が自由であることを前提としているからである。
たとえば、道徳的善悪は、自分の行動をコントロールし、その行動の時点で、正しく行動するかしないかを自分の力で決定できる自由行為者にのみ適用される。カントによれば、これは単なる常識である。その理由は、結局のところ、これらの運動の原因が時間の中で起こるからだとカントはいう。ところが、「すべての出来事には、それ以前の時間に始まる原因がある。その原因も時間内に起こる出来事であるならば、その出来事にもさらに以前の時間に始まる原因があるはずだ。すべての自然現象は時間の中で起こり、遠い過去にまで遡る因果の連鎖によって徹底的に決定される」――といった、強い意味で決定論的な自然には、「自由の余地はない」。
こう考えると、泥棒が窃盗を犯すという選択をしたのが時間的に自然な出来事であるならば、それは遠い過去にまで連鎖した因果の結果である。しかし、過去は今、現在、彼の手には負えない。過去が過去である以上、それを変えることはできない。カントの考えでは、過去に起こった出来事によって自分の行動が決定されるのであれば、現在において自分の行動はコントロールできないことになる。たとえ過去の出来事をコントロールできたとしても、今それをコントロールすることはできない。というのも、彼の行動の因果的な先行要因は、結局のところ彼の誕生以前にまでさかのぼるからである。つまり、泥棒が窃盗を犯すという選択が時間的に自然な出来事であるならば、それは今も昔も彼のコントロールできることではなく、彼は窃盗を犯す以外のことはできなかったことになる。その場合、彼に道徳的責任を問うのは間違いということになる。
自由と信念
つぎに、もう少し自由について考えることで、信念との関係をみてみよう。それには、スタンフォード大学の概説が役立つ。そこでは、つぎのように書かれている。
「超越論的な意味において、私たちは自由であることを知ることができるのだろうか。カントの答えは厄介である。一方では、理論的知識と道徳的に正当化された信念とを区別している。私たちは、私たちが自由であるとか、可能な経験の限界を超えた何かについて、理論的知識を持っているわけではないが、私たちがこの意味で自由であると信じることは道徳的に正当化される。一方、カントは自由について論じるとき、これよりも強い言葉も使っている。たとえば、彼は、思弁的理性のすべての観念のなかで、自由は、私たちが先験的に知っている唯一の可能性であると書いている。カントはこの箇所の脚注で、「自由がなかったら、道徳律は私たち自身の中でまったく出会うことがなかっただろうから」、私たちは自由をアプリオリに知っているのだと説明している。このためカントは、道徳律が自由の客観的な、「ただ実際的な、疑いようのない現実性を証明する」と主張する。つまりカントは、私たちは自由の現実についての知識をもっているが、それは実践的な現実についての実践的な知識であり、「実践的な目的のためだけの」認識であり、経験や経験の条件についての考察に基づく理論的な知識とは区別されると言いたいのである。私たちの自由に関する実践的知識は、代わりに道徳律に基づいている。カントの強い表現と弱い表現の違いは、主に、カントの強い表現が、自由についての私たちの信念や実践的知識が揺るぎないものであることを強調し、それがひいては神や魂の不滅性についての他の道徳的根拠に基づく信念の支えとなることを強調している点にあるように思われる。」
そう、神や魂についてを信じる自由は、あくまで実践的な現実についてのの実践的な知識であり、そうした実践的な知識が揺るぎないのは、道徳的根拠に基づく自由であり、信念だからというのである。
カントは、私たちが道徳律を意識すること、道徳律が私たちを縛る、あるいは私たちを支配する権威を持っているという自覚を、「理性の事実」と呼んでいる。つまり、カントの見解では、理性の事実とは、私たちが自由であると信じる実践的根拠、あるいは実践的知識なのである。カントは、この道徳意識は「否定できない」「アプリオリ」「不可避的」なものだと主張する。
すべての人間は、良心、道徳に関する常識的な把握、そして自分が道徳的に責任を負っているという確固たる確信を持っている。道徳の権威の源泉については、神、社会通念、人間の理性など、それぞれ異なる信念をもっているかもしれない。特定の状況において道徳が何を要求するかについて、私たちは異なる結論に達するかもしれない。また、自分の義務感に反することもあるかもしれない。しかし、私たちはみな良心をもっており、道徳が自分に適用されるという揺るぎない信念をもっている。カントによれば、この信念は正当化することも、「いかなる演繹によっても証明する」必要もない。私たちが自分自身に道徳的な責任を負っているというのは、人間に関する根源的な事実にすぎないのだ。
しかし、カントはここで規範的な主張も行っている。それは、我々が道徳的に説明責任を負っているという事実でもあり、道徳が我々に対して権威をもっているという事実でもある。カントは、哲学はこの常識的な道徳的信念を擁護する仕事に携わるべきであり、どのような場合であれ、我々はそれを証明することも反証することもできないとしている。
『判断力批判』
『判断力批判』は、理論哲学の領域(主に『純粋理性批判』で論じられている)と実践哲学の領域(主に『実践理性批判』で論じられている)とを隔てる「溝」や「裂け目」を埋めることによって、「(自分の)批判的事業全体に終止符を打つ」ことを目的として書かれた。
スタンフォード大学の概説は、カントの主張をつぎのようにわかりやすく説明している。
「カントがここで明確にしている問題を理解する一つの方法は、啓蒙主義の危機という観点からもう一度考えてみることである。その危機とは、近代科学が伝統的な道徳観や宗教観を損なう恐れがあるというものであり、カントの回答は、理性に主権が認められ、実践的理性が思弁的理性よりも優位に立つとき、実はこれらの人類の本質的利益は互いに一致するのだと主張することである。しかし、カントがこの回答を展開している超越論的観念論的枠組みは、世界とそのなかでのわれわれの位置についての統一的な見方を犠牲にする代償として、これらの利害の一貫性を買っているように思われる。もし科学が外見にのみ適用され、道徳や宗教的信念がそれ自体、あるいは「超感覚的なもの」に言及するのであれば、私たちはどのようにしてこれらを統合し、一方の領域から他方の領域へと移行することを可能にする世界の単一の概念にすることができるのだろうか。カントの解決策は、第三のアプリオリな認識能力を導入することである。カントはこれを「判断の反映力」と呼び、世界に対する遠隔論的視点を与える。反省的判断力は、自然と自由の間の隔たりを埋めるテレオロジーや目的性の概念を提供し、カント哲学の理論的部分と実践的部分を一つの体系に統合する。」
このカントの統合は、自然から最終原因を追放し、その代わりに自然を、数学的に完全に記述することができる運動する物質以外の何ものでもないものとして扱う、近代哲学の支配的な系統に同調する一方で、本質的に目的論的な人間の主体性の概念とを調和させる試みとみなすことができる。
このとき、カントは、(自然における)理解と(道徳における)理性の両方の自律性を維持し、どちらか一方が他方の領域を侵害することを許さず、しかも両者を一つのシステムの中で調和させようとする。この調和は、自然がどのように客観的に構成されているか(それは理解の仕事である)、あるいは世界がどのようにあるべきか(理性の仕事である)を判断するのではなく、単に我々の認識を体系的に統一されたものとみなすことができるように規制したり反省したりする、独立した立場からのみ調律することができる。カントによれば、これが「反省的判断」の仕事ということになる。
まあ、こんなメモ書きをしてもても、厳密に理解できたことにはならない。それでも、カント哲学のおかげで、科学が救われた一方で、信念もまた救われたことになる。その信念のあり方をめぐっては、ほとんど書き終わった『アメリカなんかぶっ飛ばせ』で考察しているので乞うご期待。




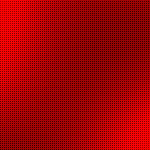




[…] のは事実である。それは、カントの主張を思い起こせば理解できる(この問題は紙幅の関係で割愛する。関心のある方は拙稿「カント生誕300年を迎えて想うこと」を参考にしてほしい)。 […]