『ハリネズミと狐』を読んで
『ハリネズミと狐』を読んで
Isaiah Berlin, The Hedgehog and the Fox, an Essay on Tostoy’s View of History (London, Weidenfeld and Nicolson, 1953)の翻訳、『ハリネズミと狐:『戦争と平和』の歴史哲学』河合秀和訳, 岩波文庫, 2018(第三刷)を読みました。なかなか興味深い本だったので、ここで紹介したいと思います。
哲学者のアイザイア・バーリンは、自由には積極的自由と消極的自由があると主張したことでよく知られています。
積極的自由は自己が自己の選択を支配する主人であるとみなし、自己支配を前提にしています。この積極的自由は自我を支配する層と支配される層へと二重化する。つまり、高次の自我は超越的で理性的であり、低次の自我は感性的な経験的自我を意味するのです。理性を体現する高次の自我がさまざまな偶然的な欲望に翻弄される経験的な自我にとって、外的な権威とみなされるようになります。ひとりの人間の内側で起きるこの支配・被支配の仕組みは人間の外部にある諸制度による支配の正当化に結びつく。
自己が自己の選択を支配する主人であるとして、その自由を行使すると、外部の諸制度を理性として受け入れた高次の自我が経験的な自我だけでなく、自己の外部にいる他者を巻き込む形で支配しようとしてしまうことになります。だから、この積極的自由を正当化すると、支配者にとっては自由を拡大解釈することが可能になり、他国を植民地化したり他国民を奴隷のように隷属状態に貶めたりしてもかまわないという独善に陥りかねません。さすがに、こうした積極的自由をいまでも正しいと主張する人は少数者でしかありませんが、それでもときとしてこうした積極的自由を主張する強者がいます。ジョージ・W・ブッシュが自由と民主主義の名の下に、2003年からイラクに始めた戦争は、こうした積極的自由をあくまで自分の都合で一方的に主張した悪例と言えるでしょう。
消極的自由
選択肢が過度に減少すれば、自由がないように思われるのは当然でしょう。だが逆に、選択肢が過度に増えると、かえって不自由に感じるというのも事実です。これが消極的自由というものです。これは他者からの干渉のない状態を意味し、それが過度の選択肢を認める状態につながっているのです。テレビCMでも流れていたとおり、まったく同じ商品について、20色も30色も違った色の外観だけを差別化した商品のなかから、一つを選べて言われても、困ってしまうでしょう。つまり、選択肢が多すぎると、かえって選択しにくくなるから、自由でないかのように感じられる。それが消極的自由です。
ハリネズミと狐
とはいえ、紹介した本はバーリンの有名な自由論とはまったく関係ありません。この話は、ギリシアの詩人アルキロコスの詩作の断片に、「狐はたくさんのことを知っているが、ハリネズミはでかいことを一つだけ知っている」という1行からインスピレーションを得て、バーリンがレフ・トルストイをどちらに分類すべきかを論じているのです。
たとえば、大胆に分類すれば、ダンテはハリネズミ、シェークスピアは狐に属しているというのです。プラトン、パスカル、ヘーゲル、ドストエフスキー、ニーチェなどはハリネズミであり、ヘロドトス、アリストテレス、モンテーニュ、ゲーテ、プーシキン、バルザックは狐ということになります。この分類からみて、トルストイはどちらなのか、それがこの本の主旋律です。その「明確で直截な答えはない」と書かれています。
『戦争と平和』という題材
トルストイの実像に迫るために、バーリンはその著作『戦争と平和』について語っています。そこできわめて興味深いのは、「個々人の生活に関するものだけが現実的であるというトルストイの信念と、その分析だけでは歴史の進路(つまり社会の行動)を説明するには不十分であるという彼の理論との間の、解決されざる矛盾」をはらんだ作品こそ、『戦争と平和』だという指摘です。前者の信念は、「ある感情の特殊な風味、正確な質――その「振れ」、退潮と満潮、微細な動きの振度――外見と思想と感傷の痛みだけでなく、ある一つの状況やある一つの時期全体、あるいは個々人、家族、社会、全国民の生活の連続した断片」を描くことにつながっています。他方で、トルストイは「広大な統一的全体性にもとづいて、そのような現実の存在を信じていた」のです。こちらは、「単一の包括的なヴィジョン」の提唱につながります。「『戦争と平和』では善人、単純で自発的で開かれた魂の基準に還元することを説いた」のです。
科学主義批判
トルストイは、「生起しつつあるもの」を、「文字通り無数の確認しがたい鎖の環――そしてまた、目に見えたり見えなかったりの裂け目と突如として生じる断絶――によってつながったり切れたりしている、事件と対象と特徴との、濃密で不透明で複雑にもつれた蜘蛛の巣と考えている」。ゆえに、それは「いっさいの明晰な論理的、科学的理論構成――人間理性が明確に描き出した対称形の型――を上滑りで薄っぺら、空疎で「抽象的」、そして生きとし生けるものの記述、分析いずれの手段としてもまったく有効でないものにしてしまうような現実の見方」ということになります。その意味で、わずかなことしか知りえないのに、神のようにふるまう科学を、トルストイは断罪したのです。統一的全体性を信じてはいても、それはシベリアの大地を生き抜く智慧をもった農民の魂に宿るとみなした。神は、「騒々しい民主的宣言や憲法の定式の空騒ぎの中にではなく、また革命的暴力の中でもなく、「自然」の法の支配する永遠の自然秩序の中で動いている」と考えたのです。
チェスの話
ここで、バーリンの書いたチェスの話を紹介してみましょう。AIの発展のような21世紀の現実を思い浮かべながら、やや長い引用を熟読玩味してほしいと思います(pp. 134-136)。
**********************
たとえばチェスにおいては、順列の数は有限で、定石は明らかであり――われわれによって、人為的にそうであるように仕組まれているのだから――、したがって組合せは計算することができる。しかし、もしこの方法を現実世界の漠然とした豊かな織り目に適用し、手持ちの因果律や確率論等々の知識にもとづいて、あれこれの実現されなかった計画や実行されなかった行為の意味合い――後の事件全体にたいする影響――を展開しようとすれば、識別した「微小」の原因の数が多ければ多いほど、そのそれぞれを一つ一つ「取りはずす」ことの帰結を「演繹」するという課題が途方もなく困難になってくることに気付くであろう。その帰結の一つ一つが、残りいっさいの計算不可能な事件と事物の全体に影響してくるからである。
チェスとは違って、それは有限の恣意的に選ばれた概念とルールによって定められてはいない。そして現実の生活であれ、さらにはチェスにおいてであれ、基本的な観念――空間の連続性、時間の分割可能性などにみだりに手を加えはじめるならば、直ちに象徴が機能を喪失し、思考が混乱し麻痺してしまうような段階に達するであろう。したがって、事実とその連関についてのわれわれの知識が十分であればあるほど、かわりの可能性を思いつくことがそれだけ困難になり、われわれが世界を把握し記述する観点――あるいは範疇――が明確で正確になればなるほど、われわれの世界の構造は固定化し、行為はそれだけ「自由」でなくなるように思えてくるだろう。このような想像力と、そして窮極的には思考それ自体の限界を知ることは、世界の「仮借ない」統一的な型に直面することである。われわれがそれと一体化していることを認識し、それに服従することは、真理と平和を見つけ出すことである。これはたんなる東洋的宿命論でもなければ、当時の有名なドイツの唯物論者、トルストイの世代のロシアの革命的「ニヒリスト」によって深く崇拝されていたビュヒナー教授とフォークト教授、あるいはモレスコット博士らの機械論的唯物論でもない。また神秘的なひらめきや統合への憧れでもない。それは細心なまでに経験的、合理的で、強固な精神にもとづいており、リアリスティックである。しかし、情緒のうえでその原因になったものは別である。それは、ハリネズミのやり方で物を見ようと強く意図している狐が、生活の一元論的なヴィジョンを情熱的に求めていることにあった。」
**********************
結局、なにが言いたいかというと、AI問題はトルストイが19世紀後半にいだいたロシアの近代化問題とよく似ているということです。たぶんトルストイが書いた『戦争と平和』や『アンナ・カレーニナ』を21世紀のAI導入問題を意識しながら読めば、なにが問題なのか、さらに、どう解決すべきかのヒントが得られるのではないでしょうか。
わたしのゼミでは、長くドストエフスキー著『カラマーゾフの兄弟』、江川卓著『謎ときカラマーゾフの兄弟』、高野史緒著『カラマーゾフの妹』を夏休みに読み、感想文を書く宿題を課してきました。これからは、トルストイの『戦争と平和』および『アンナ・カレーニナ』を21世紀の大変革を背景に読解するよう、宿題を出したいと考えています。





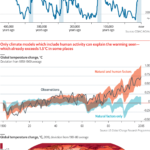


最近のコメント