「信頼」をめぐって
「信頼」をめぐって
8月に出版する『サイバー空間における覇権争奪』(社会評論社)のなかで、「神信頼」、「人間信頼」、「国家信頼」、「マシーン信頼」への変遷についてのべている。紙幅の関係で、十分な論理展開を深めることができなかったので、ここでもう少し、「信頼」について考えてみたい。余談だが、私は日本銀行の金融記者クラブに在籍した際、信託銀行を担当したことがあり、爾来、「トラスト」に大変興味をもった。すでに、拙著にも書いたことだが、1990年ころに「フィデュシャリー」という言葉にも出会えた。つまり、もう30年近く、「信頼」にかかわる問題に関心を持ち続けてきたことになる。
経済学の分野では、信頼の重要性は“social capital”という言葉によって知られている(ジェームズ・コールマンの“Social Capital in the Creation of Human Capital,” American Journal of Sociology, 1998やロバート・プットナムの“The Prosperous Community: Social Capital and Public Life,” American Prospect, 1993などを参照)。その後、サミュエル・ハンティントンの” “The Clash of Civilization?” Foreign Affairs, 1994によって文化の差の違いが重視されるようになり、フランシス・フクヤマは『信頼』(Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, A Free Press Paperbacks Book, 1995)を著した。
ここでは、フクヤマの『信頼』をもとに、この問題について考えてみよう。彼は、「国家セクターの意義は文化によって大いに異なっている」と指摘している(p. 16)。その文化は信頼関係の醸成に深くかかわっているのだ。やや脱線すると、拙著『サイバー空間における覇権争奪』において、文化に注目したのは伝統が培った生活慣習を「歴史的堆積物」と呼び滓(おり)とみなしたうえで、それが簡単に溶け出すことを予測していたアントニオ・グラムシに注目したからである。文化の問題がときの覇権国を通じて、世界全体に影響をおよぼしてきたことを忘れてはならない。
具体的には、世界の覇権国になりつつあった英国議会は1807年、奴隷貿易の廃止を決めた。1833年に帝国内での奴隷制が廃止された。米国の奴隷制廃止は1865年だ。フランスはフランス革命後の1794年に一度、奴隷制を廃止したものの、ナポレオン・ボナパルトはこれを復活した。しかし、1848年の二月革命により再び廃止された。インドの奴隷制廃止は1843年、ブラジルでは1888年、中国では1906年である。覇権をもっていた英国の政策はゆっくりとだが、着実に世界に広がった。
他方で、反腐敗闘争の国際化は1977年に施行された米国の海外腐敗行為防止法にはじまる。外国公務員への贈賄禁止などを規定した法律が生まれたことになる。1970年の威力脅迫および腐敗組織に関する連邦法にみられるように、麻薬関連の組織犯罪への厳しい規制という風潮を背景に、さらに、国家を超えて活動するようになった「超国家企業」が傍若無人に振る舞うことが米国を代表とする先進国の国家主権を侵害しかねないという基本認識が広がっていたことが重要だ。たとえば米国系企業の国際電信電話会社(ITT)は、1970年チリ大統領選挙において、左派候補で重要産業の国営化の推進をめざしたサルバドール・アジェンデの落選工作を行ったとされている。大統領就任後、ITT系企業は国営化されたが、1973年9月、アジエンデは軍事クーデターで自殺に追い込まれる。米ソ冷戦下で、こうした民間企業の暴走を阻止するために反腐敗政策の国際化が急務となったわけである。ただし、米国だけでこんなことを決めても国際取引では米国企業が不利になるだけだから、米国は主導で、1992年に経済協力開発機構(OECD)の「OECD(経済協力開発機構)・国際ビジネス取引における外国公務員に対する賄賂闘争条約」(OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 通称: 外国公務員贈賄防止条約)を発効させた。こうしたことが可能だったのも、米国が覇権を握っていたからにほかならない。
現在、覇権が揺らぎつつあるものの、依然として覇権を握っているかにみえる米国では、ドナルド・トランプ大統領の登場を機に、その覇権が大きく傾こうとしている。それは、「国家信頼」の後退、「マシーン信頼」の隆盛となって現出している。
なぜ「信頼」に興味をもったのか
ここで、信頼そのものについて考える前に、もう一点、指摘しておきたいことがある。それは、「なぜ「信頼」に興味をもったのか」という問題についてである。フクヤマは、つぎのように指摘している(p. 40)。「多くの共産主義社会の経験は、民主主義あるいは市場経済の強化を多いに遅らせた多くの習慣――企業家的エネルギーの不在につながる国家に対する過度の依存、非妥協性、および、会社ないし政党のような集団における自主的な協力への嫌悪――を創出したということである」というのがそれである。ソ連およびロシアの問題を専門としてきた私にとって、この指摘はきわめて重要な意味をもっていた。「文化」の問題として、共産主義および共産主義崩壊後を考える必要性を強く印象づけたのである。別言すれば、イデオロギーばかりが先行する見方に辟易していた私に、生活慣習のレベルでの考察の重要性を教えてくれたことになる。
たとえば、拙著『サイバー空間における覇権争奪』のなかで指摘したように、中国共産党は数千年つづいてきた中国の文化を破壊することで、共産党への従属を強いる体制づくりをはかった。その典型がいわゆる「一人っ子政策」の採用であろう。家族法を制定したり、複婚の非合法化などを進めたり、家族ではなく共産党への忠誠心を高めようとした。その政策は必ずしも成功しなかったが、「家族主義」は大いに破壊されたのである。
同じように、ソ連共産党もロシアの文化を破壊した。そこで重要な役割を果たしたのが「チェーカー」と呼ばれる「秘密警察」であり、その「遺伝子」、「ミーム」を受け継いでいるのがいまの連邦保安局(FSB)なのである。だからこそ、私はFSBに対する大いなる関心を持ち続けているし、拙著『ネオKGB帝国』(一部できわめて高い評価を受けている)を著したのだ。
もちろん、日本でも、明治政府によってそれまでの文化が大いに破壊された。「革命」とは、文化の破壊につながるほどの大変革を呼ぶと考えれば、近代化という「革命」は文化の破壊を必然的に随伴していたことになる。
フクヤマはつぎのような興味深い指摘もしている(p. 189)。
「共産主義国家は不断のプロパガンダ、教化、脅しを通じてより大きな社会集団に対する同じ感覚の道徳的義務を教え込もうとした。この種のイデオロギー的脅しは人々を仕事に動機づけるのに非効率であっただけでなく、シニシズムを広く行き渡らせるのを促した。共産種具崩壊以降、そのシニシズムは東欧や旧ソ連における仕事の価値、公的精神、市民権の目立った不足という結果をもたらした」
こうした観点から、「移行経済問題」を考えなければならないはずなのだが、残念ながら、日本でも欧米でも、こうした視角をもった学術的研究は極端に少ない。
Sociabilityの三つの経路
依然から、“society”や“social”の翻訳をめぐる考察については紹介してきた。その点を確認しなければ、ここでいう“sociability”の意味を理解することはできない。“society”を「社会」と訳したことについては、「日本では会社と社会とは相対的に別のものとして受けいれられ、反対概念として考えられています。これは明治の官僚政府が、会社と社会とが同一では都合が悪かったということから由来した造語です」と、空手指導者にして優れた思想家であった廣西元信が指摘している(廣西元信,『資本論の誤訳』, 国分幸編、[こぶし書房, 2002], 23頁)。
「ソーシャル」は“society”の形容詞である。この“society”は、個人を中心にみて、会社、社会を含む広がりをもった空間をイメージしている。だからこそ、「社交ダンス」と翻訳される“social dancing”にも「ソーシャル」という言葉が使われている。自分(個人)を中心に、自分以外の他者がいれば、そこには「ソーシャル」な関係をみることができる。しかし、そのためには「個人」が必要になる。こうした意味で、福沢諭吉が明治8年(1875)刊行の『文明論之概略』において“society”を「人間交際」と訳したのは決して間違いではなかった。むしろ、原義に近い優れた翻訳であったと言えるのだが、“individual”を「個人」と訳すことも困難であった日本では、混乱が生じたのである(個人の訳語は、1884年[明治17年]、文部省訳『独逸国学士佛郎都氏国家生理学(第二編)』に登場)。この混乱に乗じるかたちで日本では、きわめて憂慮する事態が起きた。こうした“society”のもつ概念を歪め、個人や会社を超えたわけのわからない広がりである「社会」だけに限定して使うようになったのである。当初、“society”は「仲間」、「会社」、「人間交際」といった具合に、原義に近い形で翻訳されていた。あるいは、1872年の中村正直によるミルの翻訳書『自由之理』でも、“society”の訳語として、「政府」「仲間」、「会社」などが使われていた。だがその後、「会社」や「団体」という意味を“society”に持たせるのを意図的に回避するような動きがあったのだ。その結果、「社会」というとき、そこに会社や個人が含まれているという意識が薄れてしまった。
ところが、ハンナ・アーレントによれば、「ソーシャル」はローマ起源の言葉であり、「人びとが他人を支配したり、犯罪をおかしたりするときに団結するように、ある特別の目的をもって人びとが結ぶ同盟を意味していた」、ラテン語societasの派生語である点が重要だ(Hannah Arendt, The Human Condition, [University of Chicago Press, 1958]=志水速雄訳, 『人間の条件』, [筑摩書房, 1994], 45頁)。加えて、ジョン・ロックは17世紀後半に書いた『統治二論』の第二部において、“The first Society was between Man and Wife”と書いている(John Locke, The Second Treatise of Government, An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government, 1680-1690, ∬78-79 = The Second Treatise of Government, edited by Laslett, Peter, [Cambridge University Press, 1988], p. 319)。“Man”と“Wife”が、“individual”(個人)として前提されている点が重要である。まさに、個人を前提にして、夫婦の関係から出発し、家族へと広がり、会社へと広がる「仲間」として、“society”がイメージされていたことになる。
このようにみてくると、“sociability”とは、「仲間の広がり」をつくる能力にかかわっていることがわかるだろう。その広がりをつくるには、三つの経路があるとフクヤマは指摘している(p. 62)。第一の経路は家族や血族関係に基づくものであり、第二は学校、クラブ、専門組織のような、血族関係の外側にある自発的アソシエーション(註1)に基づくものであり、第三が国家に基づくものということになる。
「鉄道信頼」ということ
ここで、“sociability”に鉄道がどうかかわってきたのかという問題に転じてみよう。こんな問題の立て方をすると、違和感をもつかもしれないが、私は「ネットワーク」に注目して、こうしたネットワークがどう変化してきたかを論じたことがある。その内容はまだ本にはしていいないが、そのなかで、活版印刷術の発明により、本などを通じた新しい形態によるネットワーク化がもたらした変化、鉄道によってネットワークが大変貌したこと、そして鉄道路線に沿って電信が普及したことで新しい変化が生じたことについて解説している。さらに、コンピューターおよびそれらが接続し合ったインターネットによるネットワーク化がもたらした変化について検討し、そのうえで、今後、21世紀が直面するネットワークに絡む新たな事態について考えた。
1790年、すべてのアメリカ人の9割が多かれ少なかれ自己充足する家族による農場で働いていたにすぎない。1830年になっても、会社の規模は小さく、マサチューセッツのウォルサムにある繊維工場が300人の従業員をもち、それが米国最大であったという(Fukuyama, p. 273)。しかし、鉄道はこうした小規模企業ではなく、大規模企業を生み出す。1891年までに、ペンシルヴァニア鉄道は11万人の従業員を雇うまでになる。米国の場合、主として個人が鉄道を所有し、運営したから、鉄道建設のための莫大な資金調達のために、大規模な金融機関が必要となった。しかも、鉄道は州をまたいで敷設されたので、米国全体を一体化するのに大いに役立った。だからこそ、米国の鉄道は米国全体にさまざまなかたちで大きな影響をおよぼすのだ。
州ではなく、米国全体としてビジネスを指向できるようになった結果、スタンダード石油やUSスティールなど、大規模会社が相次いで誕生するようになる。輸送については、鉄道に安心して任せればいいということになり、さまざまなメーカーはその製品の流通網の支配権だけに着目して全米にビジネス網を広げるようになる。それが大規模会社化を促したわけだ。
鉄道は貨物輸送によって内陸部の農産物や原材料を沿岸に輸送し、海外などに販売する方途となる。河川に沿って発展してきた都市とは違う都市が内陸につぎつぎにできることにもなるのだ。なにしろ、鉄道は人間も運ぶことができるからだ。鉄道時代の幕開けと呼ばれる米国の1830年には、人口2000人以上の町は90しかなかったが、1860年までに392まで増加した。鉄道沿線で人口が増加し、都市化に伴う問題を引き起こすことにもなる。都市に安い労働力が集まり、それを使った大規模工場が運営され、さまざまな産業が勃興する。同時に、水の確保はもちろん、住宅不足や衛生問題などが浮上する。まさに、鉄道がこうした近代化=産業化を推し進めたわけだ。
列車の出発時刻や到着時刻を正確に把握できなければ、鉄道の円滑な運行は不可能だ。このため、鉄道はその運行を中央集権的に管理することによって衝突事故を回避するようになる。19世紀半ば、アメリカ中に約100の「サン・タイム」(日の出をもとに時刻を決めるものです)と呼ばれる地方ごとに異なる時刻があった。州をまたいで鉄道を運行する際、大変なリスクをかかえていたわけである。とくに、鉄道は当初、単線が多かったため、時間厳守によって車両運行を管理しなければ衝突の危険があった。だからこそ、1872年に複数の鉄道会社が集まって時刻の統制を協議するようになる。しかし、問題解決には時間がかかり、1883年11月18日からようやく鉄道標準時が導入されるに至る。アメリカ(カナダの一部を含む)を五つのゾーンに分けて時刻を決めるようになったのだ。その後、秒針まで取り付けられた時計が出現するようになり、抽象的な量としての時間概念が細分化され、しかも支配的になる。
この鉄道運行のための時刻統制問題と同じことが社会全体に起こる。鉄道の集権的管理方式は大規模工場の経営にも影響を与えた。工場を所有する資本家は自分のもつ懐中時計にしたがって工場の労働時間を一元的に管理するようになる。17世紀にゼンマイ式の懐中時計が普及するようになっていたから、工場ごとにバラバラに時刻設定が行われるようになった。これは、資本家が教会といった共同体に代わって、資本家個人のレベルで時間を自由に創出できることを意味し邸宅が、自己の内面に意識をつくり、意識によってとらえる時間と、機械を媒介にして固有の動きを示す時間とを分離してとらえることを促したことになる。後者は共同体から離れて、機械に基づく自由な時間を所有するという観念を広げたわけだが、その自分だけの時間が逆に、バラバラになってしまった人間に客観的な時間を必要とさせるようになる。労働時間を賃金支払いの規準とするようになった資本家が時間をごまかさないようにするためにも、時間を平等にするための「客観化」が必要になる。まず、国内の時刻を統制する必要が生まれ、つぎに国際標準時が必要になった。1885年、国際子午線会議で、英国のグリニッジ子午線を基礎子午線とした国際標準時の制度が創設された。
ほかにも、米国での鉄道の隆盛は法律をも変えた。ここでは、その詳細は割愛するが、こうしたさまざまな影響をおよぼした米国の鉄道は、いわば「鉄道信頼」を生み出す。そして、それがすでに指摘したように、輸送は鉄道に任せて、製造業者はその販売のための流通経路にだけ特化できるように促した。つまり、“sociability”の生み出すネットワークは米国社会全体に大きな影響をおよぼしたのである。だからこそ、「信頼」についてよく考えてみることが必要なのだ。
もうかなり「信頼」について書いてきた。また、機会をみて、再びこの問題について取り上げることにしたい。
「21世紀龍馬」は、「信頼」について心に留めておいてほしい。単独者であった坂本龍馬であっても、「信頼」できる人物を何人ももっていた。そのネットワークが変革に役立ったとも言える。「再論、信頼」を乞うご期待。
(註1) アソシエーションという概念も一筋縄ではゆかない。マルクスは社会主義(本書でいう社中主義)を、経営者と労働者の連合(アソシエーション)に基づく生産を前提に考えていた、というのが紹介した廣西元信の主張である。このアソシエーションを、マルクスはフランス語のアソシャシオンから借用したという。アソシエーションは組合、会社という意味をもった言葉である。本書で指摘したように、「社中主義」を意味するsocialismの段階では、連合的株式会社が存在し、まだ株主に配当という「利子」を払いつづけるので、資本所有から完全に解放されたわけではなく、共産主義になって資本所有から解放されると考えたことになる。つまり、socialismには、民間の会社の息の根を止めて国有化するなどという発想はそもそもなかった。ところが、ロシアのレーニンは、「社会全体が、平等に労働し平等に賃金をうけとる、一事務所、一工場となるであろう」と、社会主義社会を構想した。マルクス自身も、『哲学の貧困』のなかで、「社会全体は、社会にもまたその分業があるという点で、工場の内部と共通点をもっている。近代的工場における分業を典型とみなして、これを一つの社会全体に適用するならば、当の生産にとってもっともよく組織されている社会は、たしかに、たった一人の企業家だけが指導者としていて、その人物があらかじめ定められた規則に従って共同体のさまざまな成員に仕事を配分する社会であろう」とのべている。ゆえに、レーニンに誤解されたとも言えるのだが、マルクス自身は「連合体(アソシエーション)構想」をいだいていたにすぎないのではないかと思われる。いずれにしても、アソシエーションとは、人々が緩やかに結びついた「連合体」のようなものと理解すべき概念であろう。


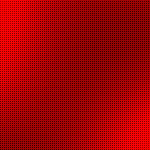






最近のコメント