信頼の再論
信頼の再論
信頼について再論してみたい。フランシス・フクヤマは、信頼が個々人のアイデンティティ(自己認識)と深くかかわっている点に注目して、アイデンティティを感じるには、①他者に認証されるという渇望、②内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づけること、③尊厳――が必要であるとしている(Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, [New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018], p. 37)。これらの条件によって個々人がなににどの程度の信頼をいだくかが決まってくるのではないか。その意味で、人間がまずはっきりと自己のアイデンティティを感じることができるかが信頼をなにに向けるか、どの程度信頼するかといった問題に関係しているように思われる。
自然、神、人間の関係について
私は2019年8月に刊行される拙著『サイバー空間における覇権争奪』の終章の注(18)において、あえて長大な注釈を書いた。自然、神、人間の関係が哲学的にどう位置づけられてきたかを論じたのである。ここでは、その内容を紹介することは控えるが、最後の部分だけ紹介しておこう。
「ここまでの説明を何となくわかってもらうには、「動物」と「人間」の関係を考えればいい。人間はもはや動物という集合に入っていないと思わせるほど、人間は傲慢になっていないか。その昔のことを考えれば、だれも人間集合が動物集合に内包されていないとは思っていなかったに違いない。つまり、動物集合から人間集合が抜け出し、動物集合と人間集合が相対峙しているかのように感じるまでになってしまったのだ。かつては、「人間動物園」(human zoo)というものがあり、人間を他の動物と同じように「展示」することが事実としてあった。だが、そうした展示も人道上の理由からなのか、こうした動物園の話は最近、ほとんど耳にしない。それだけ、人間は動物と隔絶されてしまったということだろう。」
要するに、人間は神の支配から抜け出し、動物という自然のなかからも突出するに至っている。
人類は長く神によって認証されることを渇望し、神の決めた統治システムのなかで自らの尊厳を感じようとしてきた。だが、「内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づける」ことには熱心ではなかった。すべてを神に委ねてきたからである。ゆえに、私が「神信頼」と呼ぶ時代には、他者に対する信頼よりも神と人間との間の信頼関係が優先された。だからこそ、神の「スチュアード」たる教会のような機関が信頼を集め、統治機関としての役割を果たすことができたのだ。もちろん、一神教、多神教の差もあれば、天命に支配された中国のようなケースもあったから、一般論を展開するのは困難だが、ここではこうした大雑把な議論にとどめることで先を急ごう。
フクヤマは、人間の内と外に区別を見出し、主体としての内部に重きを置く見方を可能にした、いわゆる西側の初思想家の一人がマルティン・ルターであると指摘している。これは、実は、ダニエル・ボースティンがその著書『イメージ』のなかで、「アイディール思考」から「イメージ思考」への変化が「グラフィック革命」によって促進されたと主張していることと関係している。アイディールは、無矛盾のつくりごとではない状態を意味する。人間は自らの見方や考えを神に仮託して、神のつくり出した秩序らしきものに従属させることで、神の命じる秩序を完全であるかのように受けいれていた時代の思想こそ、アイディール思考であり、そこでは、信用できるかどうかは問題にされていなかった。アイディールは無矛盾の完全な状態としてすでにあるものであり、キリスト教徒にとって受けいれるべきものとしてあったのである。
そのアイディール思考を覆したのが「イメージ思考」である。イメージはあらゆる対象の外部形態の人為の模倣ないし代理物であり、イメージは人間によって生み出される。そのとき、人間は外部を模倣し、内部にイメージをつくりあげ、外部にそのイメージを転写する。まさにイメージは、人間の内部と外部の区別が見出される契機として重要な役割を果たしたのだ。イメージは模倣や代理物である以上、その真偽が問題にされるようにもなる。ゆえに、信じるかどうかという場面に人間は数多く出会うようになる。ここに、「神信頼」の支配的な時代にはなかった、新しい信頼を構成する要素が発現するのである。それが、前述したアイデンティティを感じるための②の条件ということになる。それによって、現在にまで通じるアイデンティティを感じる3条件がはじめて整う。人間の尊厳については、神を信じることで、神によってつくり出されたものとして、人間はその尊厳を感じることができたはずだ。ただ、②の条件が生み出されたことで、人間は神ではない人間を他者として強く意識する視角を研ぎすませる。そして、外部の人間との間に「人間信頼」を築くことになるのである。
人間信頼から国家信頼へ
人間の内部と外部の区別をもっとも明確に示したものは写真術であろう。絵画は人間の内部のイメージを外部に転写し、外部に似せて描き出すことはできたが、人間の目は光を介して網膜に映し出される像を脳が認知する仕組みのなかで、絵を「本物」と感じることはできなかった。しかし、写真術によって本物を見出す感覚を得ることが可能になったことで、人間の内部と外部に差があることをまさに目の当たりにするのである。19世紀の写真術は対象を視角的に固定し客体化するもので、それは見る側と見られる側を主体と客体に峻別することを前提にしている。ここに、「リアル空間」がはじめて登場する。このリアル空間は人間の内部と外部の区別を前提に、よりリアルに見えるものを信頼する傾向を育む。いわば、人間の五感のなかで、目が特権化するのだが、だからこそその目に訴えることになる「グラフィック」の役割が高まり、それがイメージ思考をさらに深化させたのだ。
こうした技術的変化は人間の統治を円滑化する方法に大きな影響をおよぼした。アントニオ・グラムシは、社会が「支配」ないし「力」および「ヘゲモニー」の組み合わせを通じてその安定性を維持していると考えたことを思い出そう。このとき、ヘゲモニーは「知的・道徳的指導権」への合意と定義された。社会秩序は社会的境界線とルールを維持するために暴力的に権力や支配を執行する機関・集団(警察、軍隊、自警集団など)と、ヘゲモニーの創出を通じた支配的秩序ないしイデオロギー的支配(市場資本主義、ファシズム、共産主義など)への合意を説く機関(宗教、学校、マスメディアなど)によってつくり出され、また再生産される。前者は近代国家の合法的暴力装置となり、後者は義務教育やマスメディアを通じた文化による支配につながっている。ミッシェル・フーコー流に言い換えれば、国家の主権化は、規律を特徴づけている権力の手続き、すなわち処刑としった暴力に基づく「人間の身体の解剖学的政治学」(解剖-政治学)と、人間の繁殖・誕生、死亡率、健康水準などに介入し管理する、「人口の生に基づく政治学」(生-政治学)から構成される。いずれの場合でも、二つをともに支配下に置く主権国家の登場こそ、人間信頼を新たな局面に向かわせる。
ここでは、トマス・ホッブズの社会契約論だけを確認しておきたい。人間には神のつくったままの自然状態において、自然権、生存権、幸福追求権があり、それらを無制限に主張しかねない。万人の万人のための戦争になりかねない。これを避けるには、人間の自由意志に基づいて、自ら自然権を放棄したり制限したりすることが必要になる。この人間間の契約を守るには、統一された合議体が不可欠となる――という論理展開をたどるのがホッブズの社会契約論だ。ホッブズは、自分たちの人格を担わせ、その合議体による行為を自らの意志として認めることによって、群衆が一人格に統一されたかにみえるようにすることで平和と安全を維持できると主張する。この統一された人格こそ、「コモンウェルス」と呼ばれる。その人格を担う者は主権者と呼ばれ、主権者権力をもつとされる。ここに、彼は怪物リヴァイアサン(Leviathan)、すなわち「可死の神」(deus mortalis, mortal God)をみている。神はふつう、永遠で不死を特徴とするが、「巨大な権力」の象徴としてのリヴァイアサンは国家の魂の部分であり、国家自体は保護を実現する機械と化す。その意味で、それは朽ちる可能性を排除できない。ゆえに、国家は神のようでいながら、神と異なり、死ぬのである。
つまり、人間の自然権の譲渡先として現出したのが主権国家ということになる。しかも、その国家は「可死の神」として神のような存在となる。それだけ、人間は国家を信頼していることになるのだが、国家はそのように人間を信じ込ませるメカニズムを構築する。それが義務教育であったり、生-政治学に基づく「生-権力」の行使であったりするのだ。それは、国家語の制定を基礎とし、その国家語を通じて国家が歴史を教育し、国家への信頼を醸成するのだ。国家は家族、会社、学校などの集団をも国家統治に利用し、きわめて複雑な制度でがんじがらめの近代国家をつくり出す。その結果、各国の文化はアイディール思考が支配的であった時代に比べて差別化される。とくに、国家語は「ネーション」という概念と結びついて、各国ごとに普遍性を帯びているかのような誤解を生み出す。それが、文化の複雑化と他文化への不寛容となって、国家間の対立につながるのだ。
他方で、国家を担う代理人を選挙で選ぶというのが民主主義であり、その民主主義に基づく統治もまた人間信頼の方向性を国家に向かわせる。代理人になるために、選挙で勝利するには、イメージ思考をするようになった人々をうまく説得して一定の考え方に誘導することが求められるようになる。つまり、情報操作によってイメージという、曖昧なものの見方に働きかけて、統治者の有利になるような仕組みをつくり出すことが全体の円滑な統治に不可欠になったわけである。そのために、重要な役割を果たすようになったのがマスメディアだ。グラフィック革命によって誕生した新聞やラジオ・テレビなどである。そこには国家とマスメディアとの共謀関係が存在し、「合意のでっち上げ」という現象が生ずる。
こうして人間信頼は再び神のような存在として登場した国家への信頼へと傾く。それを可能にしたのは、アイデンティティを感じるための②の条件であった。他者に認証されるという渇望も尊厳も、人間が外部に向けて心を開いたり、信頼を寄せたりする大前提だが、「内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づける」には、外部環境に左右されざるをえない。その外部環境が国家によって牛耳られ、国家に有利なように条件づけられてしまうと、もはや国家を信じることが当然視されるようになる。ここに、国家信頼の強制という作用が働いているのだが、その国家信頼の強制に気づくことができるのは、国家によって尊厳を傷つけられていると感じることができるような「サバルタン」と呼ばれる、社会・政治・経済・地理的に阻害された従属者だけであったのかもしれない。逆に言えば、多くの人々は国家信頼の強制に気づかないほど、国家による教育にがんじがらめにされているのだ。
国家信頼からマシーン信頼・ネットワーク信頼へ
デジタル経済を支える先端技術の一つ、ブロックチェーンがこれまでの信頼関係とは違う信頼関係を醸成する。まあ、これ以上はここでは書かない。拙著『サイバー空間における覇権争奪』や拙稿「「デジタル全体主義」VS「デジタル資本主義」:新しい地政学に向けて」(2020年『境界研究』に収載予定)を読めば、これから先のことが書かれているだろう。

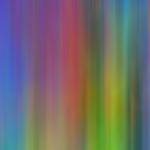


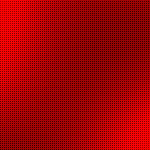




最近のコメント