「ジャニーズ帝国」をめぐるジャーナリズム論の再論
独立言論フォーラムでの連載「知られざる地政学」の第五回として、「ジャニーズ帝国」と「アメリカ帝国」:恐怖による権力支配」を書いた。この原稿は来週、送稿し、おそらく実際に公表されるのは、2、3週間先になるだろう。
そこで、このサイトにおいて、「「ジャニーズ帝国」をめぐるジャーナリズム論の再論」というタイトルで、ジャニーズ事務所をめぐる問題が教えてくれるジャーナリズムにかかわる問題について論じてみたい。
実は、私には、そうする資格があると考えている。なぜかといえば、ジャニーズ事務所による「言論弾圧」のあり様を実際に知っているからにほかならない。
ジャニーズ事務所による「言論弾圧」
そこで、先の連載の冒頭部分を紹介したい。
*************************************
「私が2020年9月から2022年3月までの間、「論座」に論考を掲載してきたなかで、もっとも多くの閲覧数を得たのは、「「嵐コンサート事件」を報道しないジャーナリズムを問う:最先端の「コンテンツ産業としてのジャーナリズム論」」という記事であった。社会的事件と呼べる出来事にほぼすべての主要マスメディアが沈黙を守ったのだ。この事件の起きた2020年の段階から、日本のマスメディアはジャニーズ事務所の支配下に完全に置かれていたのである。この事実を剔抉したのが私のこの記事であった。だからこそ、たくさんの「とまどえる群れ」がこの記事を読んでくれたことになる。こんな経験をもっているので、いまの「ジャニーズ帝国」をめぐる騒動には、考えさせられるところがある。」
*************************************
へたれジャーナリズム
「論座」の原稿に書いた内容を改めて読み直してみると、なかなかいいことを書いている。毎日、いろいろな問題について取り組んでいる私が忘れていたことが書かれている。この記事にアクセスできない人のために、少しだけ何が書かれているかを説明してみよう。
*************************************
「 2020年11月、このサイトに、「プラットフォーム独占がもたらすジャーナリズムの衰退:民主主義を死守するために何が必要なのか」という論稿を掲載した。そこで論じたのは、毎日の出来事を事実に即して報道するという、近代化後に誕生したジャーナリズムの「第四の権力」として既存権力(立法・司法・行政)を批判する精神の衰えであった。だが、ジャーナリズムがそうしたものからすでに変質し、もはやコンテンツ産業の一部でしかなくなっているとみなせば、ジャーナリズムの衰退を憂える必要はないのかもしれない。むしろ、コンテンツ産業としてのジャーナリズムに無自覚であることが問題なのかもしれないのだ。
日常生活のなかでは、ジャーナリズムがコンテンツ産業の一翼を担うだけの存在に成り下がったと意識することは難しい。しかし、11月3日に起きた「嵐コンサート事件」へのマスメディアの対応はジャーナリズムの「足腰の衰え」を教えてくれる。そして、コンテンツ産業のなかでの発言権の脆弱性も印象づけている。ゆえに、ここでは「嵐コンサート事件」を紹介し、コンテンツ産業の一部でしかなくなったにもかかわらず、その立場に自覚的でない、日本の「愚かなジャーナリズム」のいまについて論じてみたい。
ジャーナリズムの変質
まず、ジャーナリズム自体が変質しているのではないかという論点について考えたい。そこで、ある意味で、世界でもっとも最先端の議論を展開しているロシアのジャーナリズム論を紹介しよう。
2009年刊行のジャーナリズムの教科書(E・P・プロホロフ著『ジャーナリズム論入門』)をみると、ジャーナリズムの機能としてもっとも重視されているのはイデオロギー的機能である。ある階級・集団・組織などがその社会的利害を隠蔽しつつ自らの立場を正当化しようとして形成する信条・観念体系をイデオロギーとみなすソ連時代には、観念体系としての社会主義イデオロギーを喧伝するという役割をジャーナリズムが担っていたのである。もちろん、イデオロギーだけでなく、文化的、教育的、広告的、娯楽的な機能もまたジャーナリズムが担ってきた。具体的には、新聞やテレビといったマスメディア(大量媒体)がこうした機能を実践してきた。
ソ連の崩壊に伴って、ジャーナリズムが社会主義イデオロギーを喧伝する役割はなくなったが、それでも、ジャーナリズムは人々の意識、理想や願望に深い影響を与えたいという欲求をもち、社会的指向性(一種のイデオロギー)を提示するという機能を担っていると主張している。その意味で、ジャーナリズムにとってイデオロギー的機能を果たすことがもっとも重要であるとする見方はソ連時代もいまも変わっていない。
国立モスクワ大学ジャーナリズム学部の見方
ジャーナリズムを国立大学で教えるという形態は社会主義時代のソ連でも、ソ連崩壊後のロシアでも変わっていない。ただ、社会主義イデオロギーを守るという使命が失われて以降、ロシアにおけるジャーナリズムの立脚点は微妙なものとなっている。
国立モスクワ大学ジャーナリズム学部のエレーナ・ヴァルタノワ学部長の「メディアとジャーナリズムの最近の概念について」によると、自由主義の概念(言論の自由という概念)の信奉者にとっては、ジャーナリストは事実を正確に提供する義務を負っているのに対して、社会的責任の概念(ソ連の理論)の支持者にとってはジャーナリストの立場はプロフェッショナリズムを不可欠の条件としていると指摘している。
やや曖昧な表現だが、要するに、前者は資本主義というイデオロギーのもとでのジャーナリズムの機能であり、後者は社会主義イデオロギーのもとでのジャーナリズムがそのイデオロギーを守ることを専門としてきたと言いたいのであろう。彼女は、別の場所で、「新聞はプロパガンダとイデオロギーの道具であった、それは変わっていない」と発言している。
ただ、ヴァルタノワはジャーナリズムの変質を指摘する。いまのジャーナリストは「コンテンツ」の制作に従事する仕事をする人物を意味し、そのコンテンツには、広告テキスト、アート写真、映画などのテキストが共存している。ゆえに、いまのメディアジャーナリズムは単にニュースを見つけてそれを文字にしたテキストだけでなく、広告や写真などと合わせてコンテンツとして提供されているのだという。つまり、単にコンテンツ産業の一翼を担うのがジャーナリストであり、ジャーナリストは情報の作成、加工、発信、保存という作業の一部を担うだけの存在に成り下がっているのだ。コンテンツ産業のなかの広告や流通・販売にかかわる部分が力をもつと、ジャーナリストの制作するテキストが歪められたり、無視されたりしても仕方がないという状況が生まれているのだ。コンテンツ産業としてビジネスで生き残るためには、ジャーナリスト風をふかして偉そうにしてはいられないのである。
すでに、ロシアでは、こうしたジャーナリズムの変質が事実として受けいれられており、そのうえでジャーナリストが果たすべき役割が検討されている。だが、日本のジャーナリストは相変わらず、自らを「第四の権力者」であるようにみなし、たとえば、ジャニーズ事務所というコンテンツ産業の有力企業を軽視し、人気グループ・嵐など、芸能人の一団くらいにしか思っていない。だが、コンテンツ産業からみれば、かれらはビジネスに直結する「カネのなる木」であり、有力コンテンツなのだ。にもかかわらず、ジャーナリズムの立ち位置に無自覚な日本のジャーナリズムは「嵐コンサート事件」で、残念な行動しかとれなかった。」
*************************************
この文章のあとに、「嵐コンサート事件」の内容が語られている。だが、それはここでは割愛する。この記事の最後に書いたのは、つぎのようなことであった。
*************************************
そう考えると、「嵐コンサート事件」を報道しないのはまずかったと思われる。この事件を徹底的に調べて、事実に即して、新聞、テレビ、ラジオ、SNSで報道すれば、コンテンツビジネスとしての総合力を多くの若者に知ってもらえたはずだ。コンテンツ産業内であっても、ジャーナリズムの地位を確保するためには、事実に即して「道徳的明快さ」を伴う報道をすることが望まれるのである(「道徳的明快さ」については、拙稿「「道徳的明快さ」が求められるジャーナリズム:客観性、中立性よりも大切な価値から再出発せよ」を参照)。もう昔のジャーナリズム論は通用しないことをもっと自覚してほしい。最先端のロシアのジャーナリズム論くらいは知っていてほしい。
*************************************
「道徳的明快さ」をめぐって
つぎに、「道徳的明快さ」について紹介しなければなるまい。拙稿「「道徳的明快さ」が求められるジャーナリズム」において何を書いたかについて説明しよう。まず、この論考はつぎのような記述からはじまっている。少し長い引用をサービスしよう。
*************************************
いま、米国のジャーナリズムでは、「道徳的明快さ」(moral clarity)を求める動きが広がっている。人種差別問題が脚光を浴びるなかで、ジャーナリズムは「客観性」を装うのではなく、道徳的明快さから運営されるよう再構築する必要があるとの機運が高まりをみせている。米国の動きを対岸の火事としてながめるのではなく、日本のジャーナリズムへの問いかけとみて、ここでこの問題について考えてみたい。
ニューヨークタイムズで起きた事件
「ニューヨークタイムズ電子版」は6月3日付で、保守的なアーカンソー州の上院議員トム・コットンの論説「軍隊を送り込め:国家は秩序を回復しなければならない。軍は準備ができている」(https://www.nytimes.com/2020/06/03/opinion/tom-cotton-protests-military.html
)をオピニオン欄に掲載した。黒人のジョージ・フロイド殺害後に起きた、複数の都市での略奪を鎮静化するために、コットンは軍隊の使用を求めたのである。この論説の公表に対して、NYTの黒人従業員グループが主導して公表を非難する署名が展開された。米国の都市の路上での軍隊使用を求める訴えを公表することは、アフリカ系アメリカ人ジャーナリストを直接脅かすものであるとの見方もあり、スタッフの反発が起ったのだ。
注意すべきなのは、彼らが公の場での言論の停止を求めていたわけでも、自分たちの嫌いな意見を検閲することを求めていたわけでもないことである。彼らは、デリケートな時期に、突飛な事件を扱ったことに反発したのである。
NYT発行人のA・G・サルツバーガーはこの掲載が正しくなかったことを認め、オピニオン欄の編集者、ジェームズ・ベネットは辞表を提出した。ベネットは公表前にコットンの記事を読んでいなかったというのだから、辞職は当然かもしれない。
問題になったのは、編集権を握ってきた多くの白人が黒人の立場を思いやることができないまま客観性を装いつづけてきたジャーナリズムのあり方であった。
発行人のサルツバーガー自身、「我々は独立と客観性の原則から退いてうるわけではない」としながらも、「人権や人種差別のようなものについては客観的であるふりをしてはいけない」と語っている。
「道徳的明快さ」の場所からの再構築
NYTのごたごたに対して、ワシントン・ポストの白人編集長と衝突した後、同紙を去った黒人ジャーナリスト、ウェスリー・ローリーは、6月4日、アメリカのどこからともなく「客観性」にとらわれてきたジャーナリズムが失敗した実験であると指摘したうえで、つぎのようにツイートした。
「我々の分野の規範を根本的にリセットする必要がある。旧態依然たるやり方は捨てなければならない。必要なのは、道徳的明快さのある場所から運営される我々の業界を再構築することだ。」
この率直な発言が波紋を広げている。6月12日になって、NYTのコラムニスト、ロジャー・コーエンはローリーのツイートを取り上げて反論している。ジャーナリズムの「客観性」という概念を「あまり信じたことがない」としながらも、頭と心、考える明晰さと感じる情熱のバランスが必要だと説いている。これは、議論の双方に平等な重みを与えることで客観的であるように見せるための簡単な近道であり、「両サイド主義」と呼ばれている。
コーエンに言わせれば、「道徳的明快さの場所」とは、真実が一つしかなく、そこから逸脱したらおしまいという意味になるのであって、リベラルな思想に反している。自由は開かれた議論によって満たされるというのがリベラルな考えであり、たとえ反発する意見をもつ人がいても守る価値があるという。
しかし、これに対して、6月23日、ローリーはNYTに反論を掲載する。このなかで、彼は「正論」をのべているように筆者には思われる。たとえば、つぎの指摘は重い意義をもつ。
「何十年も前に、アメリカのジャーナリズムの軸足が公然たる党派的報道から客観性を公言するモデルに転換して以降、主流派は客観的な真実と思われるものを、白人記者とそのほとんどの白人上司によってほぼ独占的に決定されることを許してきた。そして、そうした選択的真実は白人の読者の感性を傷つけないように修正されてきた。オピニオンページでは、許容される公的議論の輪郭は白人編集者のまなざしを通じてほぼ決定されてきたのである。」
さらに、黒人であるローリーのつぎの指摘も胸を打つ。
「白人の意見や傾向は客観的な中立として受けいれられている。黒人や褐色の記者や編集者がそれらの慣例に挑戦すると、彼らが押し出されたり、叱責されたり、新しい機会をうばわれたりすることが珍しくない。」
中立的な「客観的ジャーナリズム」の主観性
朝日新聞社と日本経済新聞社で記者経験のある筆者としては、つぎのローリーの指摘についても正しいと心から思う。
「中立的な「客観的ジャーナリズム」は、その記事を取材するか、どのくらいの強度で取材するか、どの情報源を探し含めるか、どの情報が強調され、どの情報が軽視されるかといった、主観的なピラミッドの上に構築されていることを我々も知っている。ジャーナリズムのプロセスに客観性はない。そして、個々のジャーナリストも客観的ではない。なぜなら人間であるからだ。」
こうした事実を率直に認めるところに立ち返ったうえで、ローリーは「道徳的明快さ」の重要性を主張している。わかりやすく言えば、「警官が関与した銃撃」のような不器用な婉曲表現によって中立的な客観性を装うのではなく、「警察が誰かを撃った」と表現することが道徳的明快さにつながるということになる。
*************************************
どうだろうか。「道徳的明快さ」(moral clarity)がないために、日本のすべての巨大マスメディアはジャニーズ事務所のジャニー喜多川による性加害疑惑を追及できなかった。旧統一教会と自民党などの国会議員、地方議員との共謀・癒着についても同じである。そして、ウクライナ戦争をめぐる米国べったりの報道も同種の愚行である。中立的な「客観的ジャーナリズム」を装いながら、結局、権力や権力者におもねっているだけだ。
ここで紹介したようなジャーナリズム論をよく検討しなければ、ジャニーズ事務所をめぐるマスメディアとジャーナリズムの癒着、結託、共謀の関係を暴き、変革につなげることはできない、そう私は思う。



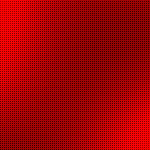




最近のコメント