笠井潔著『夜と霧の誘拐』をめぐるメモ
いつものように、読んだ本のメモとして、今回は笠井潔著『夜と霧の誘拐』についてもとめておきたい。終盤部分については、すでに「知られざる地政学」の連載(121)としてまとめたので、12月20日と21日に公表される拙稿をみてほしい。
230頁
「どう違うんですか、権力と暴力は」国家権力の一部として警察や軍隊が存在するように、常識的には暴力は権力の一部だろう。
「暴力の反対概念は非暴力ではない。暴力に真に対立するのは権力で、権力と暴力は性格として正反対の、たがいに対立する力(ピュイサンス)なの。権力が大であれば暴力は小で、逆もまた真といえる。権力の力は合意と協調による集団的な力で、人々が一緒に行動するときにはいつでもそこに権力が存在している」
カウフマンによれば合意としての権力が縮小すると、縮小分を埋めるために強制としての暴力が生じる。完全な権力は暴力を必要としないし、暴力が完全に支配するところでは権力は消滅するだろう。暴力とは目標を達成するための道具的な力だが、しかし権力は違う。人々が集まることは人間の定義に属しているからだ。したがって集団から生じる権力も、それ自体が目的だとしかいえない。不完全な権力を補完するものとして、その目的を達成する手段として暴力が生じてくる。
240頁
古代ギリシアでは動物的な生(ゾーエー)と人間的な生(ビオス)が厳格に区別されていた。食物の生産や食事に典型的な生存のための活動が不可避である点で、人間もまた生(ゾーエー)を生きざるをえない。古代アテネで生(ゾーエー)が営まれる場所は家(オイコス)だった。人間の生(ゾーエー)を支えるための労働や生産の活動は、家(オイコス)に閉じこめられた女と奴隷に委ねられた。
家(オイコス)は私的な世界だ。女や奴隷を支配する家長は、市民としてプニュクスの丘で開かれる民会に参加し、もろもろの問題を討議し決定する。民会という政治空間こそ家(オイコス)とは原理的に区別された公的な世界だった。
カウフマンの話から思いついて、わたしは口を挟んだ。「福音書の作者も同じように考えたのではないでしょうか。マタイ福音書のイエスは悪魔から、おまえが神の子なら石をパンに変えてみろと、軌跡の実演を強要されて答えます。人間はパンだけで生きるわけではない、神の言葉によっても生きると。パンの次元と神の言葉の次元の二重性ですね」それは、動物的な欲求と人間的な欲望の二重性ともいえるだろう。
老婦人が頷いた。「古典期のギリシア人は後世のキリスト教徒と違って、パンの次元に神の言葉でなく人間の言葉を対比させた。そこが決定的に違うところ」
わたしたちの話を聴いていた青年が口を開く。「カウフマンさんの語る権力の構成主体、公共空間で言葉をかわしあう主体を市民(シトワイヤン)とします。市民(シトワイヤン)は共和国を構成する政治的主体で古代のアテネにもローマにも存在しました。それは所有する富の大小など経済的属性と無関係です。
市民(ブルジョア)は経済的に規定される階級ですね。富裕な商工業者としてのブルジョアも、無産者としてのプロレタリアも経済的階級です。人間は政治的な市民と経済的な階級の二重性を生きる」
ブールもシテも都市を指している。「都市の人」という原義では、ブルジョアとシトワイヤンは同
241頁
じ意味のはずだが、実際の使われ方は異なる。ブルジョアは私人、シトワイヤンは公人だからだ。ブルジョアが経済的に豊かな市民、ひいては資本家を意味するようになったのは19世紀からだろう。近代社会でも人は、私人(ブルジョア)と公人(シトワイヤン)の二重性を生きざるをえない。
「しかし人間には第三の存在形態がある、市民でも階級でもない存在形態が。事例を古代アテネに置き直せば、民会で議論を闘わせる主権者としての市民でも、家(オイコス)に閉じこめられて経済活動に従事する女や奴隷でもない存在」
カウフマンが青年に応じる。「解放奴隷や外国人かしらね」
「むしろ逃亡奴隷でしょう。政治人としての主人のために労働する奴隷は経済人ですが、家(オイコス)から離脱してしまえばその規定は失われる。カウフマンさんの議論からは逃亡奴隷のような存在が除外されていますね。
動物も人間も喰わなければ死ぬ。個と種が存続し続けるために必要な生産、そして生殖のために人類は太古から共同体を組織してきた。共同体とは生産と生殖に奉仕する諸機能の体系です。この体系に組みこまれた諸個人とは、共同体が期待する役柄にすぎません。父と母、狩人と農夫などなど。共同体が解体してのち、近代は新たな機能体系を市民社会として組織していく」
中世的な農村共同体の外に都市が形成された。「都市の空気は自由にする」といわれたように、都市は封建領主の権力から相対的に自立していた。とはいえ中世都市の住民は、ギルドのような職業組織や地域の自治組織に厳格に組織化されてもいた。
災害や飢饉に追われ、あるいは土地を奪われた農民は共同体の絆を失って群衆化し、都市に流れこんだ。どこの誰ともしれない異形の男女が街路を徘徊したり、それらの群居地として都市の底辺に巨大な貧民地区が形成されていくのは、絶対主義王権の時代からだ。教会や貴族とは異なる第三身分と
242頁
して一括されていたが、そこには伝統的な商工業者の子孫である比較的富裕な少数の人々と、土地を奪われ飢饉に追われて農村から流入してきた膨大な貧民層の双方が含まれていた。
246頁
「ヤブキさんは三項図式を重視するようね、欲求と欲望と欲動や市民と階級と群衆など」
「ご存じのように古代ギリシア人の思考は三元的でした、たとえば肉体と魂と精神のように。しかも項と項は対立的ではなく類比的に捉えられていた。古代の類比的三言論から中間項を排除して、肉体と精神の対抗的二元論を確立したのはキリスト教で、これは地上と天上、神と人間などに変奏されていく。思惟と延長、主体と客体はその近代版ですね」
カウフマンが煙草を銜える。「父と子との人の三言論はキリスト教神学の大前提よ」
「神と精霊とキリストの三位一体論でキリストの人間性は完全否定され、父と子は実体として一体的とされました。ギリシア哲学に影響されたキリスト教的三元論は、こうして二元論に回収され終えた」
「欲求と欲望と欲動の三項は、市民と階級と群衆に対応するのかしら」
「対応するとすれば欲求と階級、市民と欲望、群衆と欲動でしょう。他の論点では古代の類比的三元論を援用するカウフマンさんが、家(オイコス)とポリスの対項的に言論に固執するのは奇妙です。動物的欲求と家(オイコス)、人間的欲望がポリスに対応するとしたら、欲動は逃亡奴隷としての群衆に体現される」
評議会的な政治はローマ帝国の民会や執政官元老院のような制度にではなく、スパルタクスを首領とする逃亡奴隷の集団の側にあった。評議会の起源は北米の先住民や雑多な移住者の共同体、あるいはカリブの海賊共同体など古くから世界のいたるところに存在してきた。カウフマンが称揚するアメリカ革命の精神は、それらを引き継いだ限りで革命的だったとカケルは語る。
老婦人が反論した。「アメリカ建国の父たちの構想に、イロコイ連邦のシステムが影響下というのは俗説ですよ。アメリカ革命の評議会的な基礎は、ニューイングランド植民地の村や町の
247頁
自治集会(タウン・ミーティング)だった。その連合体が州政府(ステート)の水準まで段階的に積み上げられていく。そこから独立戦争の民兵隊も組織されたんです」
「ニューイングランド植民者の自治集会(タウン・ミーティング)に評議会的な要素が見られたとすれば、清教徒革命の余波でしょう。清教徒による革命戦争の自己組織化はイギリス本国では実現されることなく、迫害を逃れてアメリカに移住した者たちによって部分的に試みられた。しかしホーソーンの『緋文字』で描かれているような共同体の閉鎖性、排他性は行儀快適な開放性と異質ですね。そこからセイラムの魔女狩りのような倒錯も生じた。
異端や異論の排除と抹殺は大衆蜂起の評議会ではなく、評議会に対立する革命党派の論理です。宗派主義的な神権政治に蝕まれた自治集会(タウン・ミーティング)を評議会としては評価できませんね。先住民のイロコイ連邦のほうがはるかに評議会的だった」
250頁
「僕の想定する政治にも決断は欠かせない契機として含まれます。しかし同時に政治とは技術でもある。科学技術(テクノロジー)として完成される近代的なテクニクではなく、古代ギリシア的な技術(テクネー)ですが」
「技術(テクネー)の意味はハルバッハの解釈でいいのかしら」
少し不審そうなカウフマンにカケルが小さく頷いた。「近代的な技術(テクニク)は主体が客体を加工変形するための技ですね。近代以前の技術(テクネー)はもともとあるものを形あらしめる技で、日本には興味深い話が伝えられています」
「どんな話なの」
「13世紀の優れた仏像彫刻家は、仏像の表象を木材に投影したのではない。もともと木のなかに埋まっていた仏を、木屑を払いのけるようにして取り出したにすぎないと」それは運慶の挿話だろう、カケルから日本語学習の副読本として進められた短篇集で読んだ覚えがある。
「たしかに古代的な技術(テクネー)ね、ギリシアにも似たような話はあるし。なんらかの有用な目的のため人間が対象を加工変形する技、ヤブキさんのいう技術(テクニク)をわたしは仕事(ワーク)と呼んできた。仕事が遂行されるためには、人間の側が完成品を表象していなければならない。理念的(イデアル)な設計図、たとえば彫刻の完成像を意識しながら材木を刻んだり削ったりする行為が、ようするに仕事。これは生存の必然性に規定された労働(レイバー)と、概念的に異なる行為ね」
わたしは質問した。「どう違うんですか、素材を加工変形する点では労働も仕事の一種だと思いますけど」
農夫が土地から小麦を生産する、家政婦がパンを生産する。いずれも労働で仕事ではない
251頁
とカウフマンはいう。たとえば彫刻職人が彫像を、建築職人が神殿を造るのが仕事だ。小麦もパンもじきに消費されて世界から消えてしまう。しかし彫像や神殿は労働の産物よりも永続性がある。
「わかりますが」わたしは呟いた。「漂着した孤島の大地をロビンソン・クルーソーは小麦畑や牧場に変え、テーブルや山羊皮の服や丸木船を手造りしますね。小麦粉と丸木船のあいだに、存在性格の根本的な違いがあるとは思えません」
「生存とは生きているという事実の一瞬一瞬の積み重ねなの。生存の必然性に規定された労働や労働の生産物もまた一瞬一瞬のものにすぎない。仕事による製作物は、たとえわずかであろうとも永遠性や不滅性に近づいている」
ロビンソンは近代的な生産者の理想型だ。食物の生産が主要な労働だった近代以前と、機械制大工業による消費財の大量生産は水準が違う。近代では労働が仕事化し、仕事が労働化して両者が一体化した。労働の生産物であるパンと、仕事の結果であるパン工場や製パン機械が一体であるように。
老婦人が煙草の煙を吐きだした。「近代では技術(テクニク)が科学技術(テクノロジー)として完成されていく。政治でも経済でもない第三の領域として、社会が生まれたのも近代のこと」
経済という家(オイコス)の領域が膨張し、家(オイコス)を超えて巨大化したのが社会だとカウフマンはいう。経済の場としての家(オイコス)とは異なる公共的な政治の場は、経済に駆逐される社会の従属的な一部と見なされるようになる。こうして私的領域と社会領域と公的領域の三項性が成立した。
256頁
「レーニンが愛用した『蜂起は技術である』という言葉はブランキに由来します。しかしレーニンは、ブランキ的な技術(テクネー)を近代的な科学技術(テクノロジー)に曲解した。テクノロジーとは主体による客体の操作です。客体に主体が部分的に逆規定されるような場合も含めて。運転者が自動車を運転するように、党は民衆を操縦しなければならない。もう少し違う比喩でいえば、実験者は試薬と試験管を慎重に操作して、目的とする化学反応を生じさせねばならない。いずれにしてもテクノロジーの発想ですね」
カウフマンが不愛想にかぶりを振る。「少数派の蜂起によって民衆という火薬樽に火を点けようとしたブランキは、ボリシェヴィキの先行者よ。ブランキの技術は発破の技術に似ている。巧妙にダイナマイトを扱う鉱山技師の技術もテクノロジーにすぎませんよ」
ブランキが生きた時代、19世紀パリの底辺には、農村共同体やギルド共同体の解体から生じた貧民層が分厚く堆積していた。大革命からパリ・コミューンまで、きっかけが与えられるや街路に繰り出してバリケードを築き、軍隊や警察と市街戦を戦って、市庁舎や議事堂を選挙したのは下層貧民の大群だった。
19世紀フランスの政治過程は貧民たちの蜂起によってしばしば攪乱され、七月革命や二月革命では旧権力の倒壊を惹き起こした。1789年にはじまる大革命も、1830年七月や1848年二月や1871年のパリ。コミューンなど「革命」として歴史に刻まれた特権的な事例の他にも、小規模な武装蜂起は絶えることなく試みられてきた。そこにはブランキに率いられた小規模蜂起も含まれ
257頁
る。
260頁
「二種類の自由があるのね。自由(フリーダム)と解放(リベレーション)は違う。貧困や飢饉や圧政からの自由は、解放としての自由にすぎません」
「自由とは抑圧からの自由、あるいは内面の自由なのでしょうか。道徳法則に従うことだとか必然性の洞察だとか、説はいろいろとあるにしても、わたしは意思と能力、欲求と可能の一致だと思うんです」なにかを「したい(ヴロワール)」と、それが「できる(ブヴォワール)」が一致していれば、人間は自由だといえる。「囚人が獄舎の外に出たいのに出られないとき、自由はない。あるいは空腹なのに食物がない状態も自由ではない。とすれば食物の要求は自由の要求なのでは」
老婦人が応じる。「たとえば餓えたあなたは、どこから食べものを持ってくるのかしら」
「食べきれないほど持っているのに、餓えた人を助けようとしないで見殺しにするような富者から」議論の流れで暴力革命を肯定しなければならない立場になった。
「富者から奪うわけね。手近なところに飽食している人がいなければ、同じように餓えているけれど
261頁
最後のパンを持っている、ほんの少し豊かな隣人から奪うのかしら」
「それは……」わたしは言葉に詰まった。
「どちらも同じことよ。生存の必然性に規定された行為で、労働の代替にすぎないところには。一致しない意思と能力をやみくもに一致させようとすれば、他者から奪うこと、他者を服従させることに帰結せざるをえない」
貧者が富者を襲って富を奪うこともまた、生存の論理に由来する必然にすぎない。飽食した富者の味方をする必要はないが、富者を襲う貧者の行動が自由だともいえない。フランス革命からロシア革命まで、これまでのあらゆる革命が主権の樹立をめざし、結果として新たな抑圧と貧困をもたらした事実は否定できないだろうとカウフマンはいう。
266頁
長いこと近代の哲学者は私と世界、主観と客観、内在と超越の分裂を心理の成立可能性をめぐる難問として論じてきた。それを倫理の根拠という形で掴み直したところに、月と地球の比喩の現代性がある。ようするにスタヴローギンとは、神の存在証明を失ったデカルト主義者なのだと青年は語っ
267頁
た。
倫理の不可能性の根拠として人が死の絶対性を想定するときも、死とはギュゲス(プラトンの『国家』に登場するグラウコンが物語るギュケゲという羊飼いの挿話を想起せよ:引用者注)の指輪の等価物にすぎない。透明人間を処罰することができないように、死者もまた処罰をまぬがれてしまう。
しかし同じことが月と地球の比喩で語られるとき、問題はデカルト以後のものとなる。ギュゲスは外的世界の存在を懐疑したわけではない。もしも外的世界の拘束が私に及ばないなら、私は倫理から無限に逸脱しうることを示す事例として、プラトンはギュゲスの元語りを引いている。
スタヴローギンは倫理の不可能性の根拠として、私=地球と世界=月が絶対的に隔てられていることを指摘した。デカルト以後の時代は神の存在証明を失った、壊れたデカルト主義者の大群を生みだした。近代の哲学者が一般にそうしているところの、主観と客観を対項的に指定するメタレヴェルの主観性の前提化を、スタブローギンは欺瞞であるとして拒否する。
この私は世界に到達することが禁じられている。しかも、こうした事態の問題性は真理というよりも、むしろ倫理の成立根拠において鋭く問われざるをえない。
「悪は私と他者との関係に宿る。しかし他者が存在するためには、まず世界が存在しなければならない」
わたしは口を出した。「仮に自殺が悪だとして、自殺という悪に他者は存在しないわ」
「ヤブキさんがいいたいのは、『殺す私』にとって『殺される私』は他者だということでしょうね。前者の私は後者の私を、ようするに死ぬ私や死んだ私を原理的に体験しえない」
軽く頷いて青年は続ける。「現象学の他者論に説得力がないのは、論理的な不備のためではない。感情移入の不全性や失調の根拠が明らかでないから、現象学の他者論には説得力が乏しい」
感情移入はもともと美学用語だったが、現象学では自我からの意味の移し入れによって他我が構成
268頁
されるという文脈で用いられる。現象学的に還元された世界では超越論的自我の他に別の自我、すなわち他我が存在し、それもまた独自の超越論的主観性の中心点に位置することになる。
「問題のロシア作家の時代的直観によれば、群衆の一人一人がスタヴローギンなんです。もともと共感(コンパッション)とは他者の痛みを自分の痛みとして感じることで、現象学的にいえば感情移入によって可能となる。しかし、われわれは他者に自然には共感しえない。私と同じような外見の対象が目の前にあらわれても、それを私と同じような主観とは確信できない。違う言い方をすれば、それが私と同じような心的経験を生きているとは感じられない」
どうしてわたしは、目の前の老婦人をもうひとつの主観だと信じられるのか。人間の形をしていても等身大の人形かもしれない、たとえ動いても喋っても精巧なアンドロイドかもしれない。血を流したとしても、生化学的ロボットという可能性は否定できない。発した言葉に相応の返答がなされても、人工知能が答えているのかもしれない。
「それでもヤブキさんは、わたしを自分と同じ人間だと思って話している。違うかしら」
「目の前にあるそれを人か物か決定できなくても、人であると仮定して対応することはできます。世界が本当にあるかどうかはどちらでもいい、たいした問題ではないから。
世界を世界の意味に還元することは、世界を厳密なものとして再認識するためではありません。もろもろの臆断(ドクサ)を抱えて人は生きているし生きていける。困難な問題は認識でなく倫理です。倫理の根拠を探究するために還元は遂行されなければならない。だから私と同じような外見のそれに、私と同じような心があるかどうか、この問題は決定的なんです」
「どんなふうに」老婦人は眉根を寄せる。
「心がなければ物ですね。物であれば壊すことに倫理的な問題はない。われわれは日々、無数の物を
269頁
壊しながら、あるいは壊された物を利用しながら生きています。ジャイナ教徒やヴィーガンであれば動物を壊す、すなわち殺すことを否定するとしても」
「人が人に暴力を振るいうるのは、感情移入が成立していない場合だというのね。それなら自殺はどうなの。私は私が心のある存在だと知っているけれど、これでも私を殺すことができる」
「自殺の際には私が二重化していて、心的なリアリティは殺す私の側に集中している。だから殺す私は人でも、殺される私は私ではない存在、ようするに物でしょう。感情移入は必然ではないし、私がそれをもう一人の私であると信憑しうるのは、信じられないほどに微妙な心的作用の結果です。だからいつでも人は物に変貌しうる。連続殺人者のサイコパスには人として、溢れるばかりの生き生きした意味として感受しえないタイプが多く含まれている」
287頁
神や科学的真理や市民的規範など、それまで人が行動する際に参照してきた公準や指針のいっさいが、第一次大戦の膨大な戦死者の山に圧し潰されて惨めな残骸と化した。神が失われた時代を生きる復員青年たちは、いまや無根拠に決断し行動しなければならない。決断主義とは、二十世紀の時代精神としての行動的ニヒリズムの別名でもある。
カケルは続ける。「シュミットは主権者の決断を、ハルバッハは死に先駆する決意性を語った。対戦間ドイツの行動的ニヒリズムがナチズムを思想的に準備したと、カウフマンは批判している。ドイツのナショナリズムに親和的だった決断主義と対立的な彼女の思想にも、しかし同じ時代精神が影を落としている。たとえば暴力が支配する私的空間と次元の異なる公的な政治空間とは、言論で卓越性が競われる場だという発想など」
議会主義における討議は、対立する利害の均衡点を見出すために行われる。利害対立が存在しなければ議論の必要はない。しかし代表制議会のような調整や妥協の場ではなく、卓越性を掛金とした言論の闘技場がアテネの民会、そして公的空間としてのポリスだったとカウフマンは語る。民族を自由な市民に置き換えたとしても、闘技のための闘技、闘争のための闘争は決断主義と発想を共有している。
430頁
二十世紀的な群衆といっても、国外からの難民と国内で階級脱落(デクラセ)した群衆は存在性格が根本的に異なる。後者は排外的ナショナリズムで結束し前者に敵対する。その極限的な事例が『最終的解決』にいたるナチのユダヤ人排除だった。
「どちらも根無し、故郷喪失という点は共通するけれども、二十世紀的なモブとしての群衆は後者よ」
「しかし国外からの難民が革命群衆、国内的な階級脱落(デクラセ)者が反革命群衆とも一概にはいえませんよ。ナチが階級脱落(デクラセ)化した群衆の運動だったことは事実だとしても、同じ層がドイツ十一月革命や、それに続く大衆蜂起を担い、また一九三〇年前後には共産党に流入した。この時期に激増した失業者でも、社会民主党や共産党に組織されていた産業労働者層が雪崩を打ってナチ化したとはいえません。産業労働者を基盤とした社会民主党と、南ドイツのカトリック農民層に支持された中央党の票は、29年以降も目立って減少していないし」
「そうね。ナチが喰いとるのに成功したのは保守票で、モブ的な活動家の供給源は主として階級脱六(デクラセ)化した新旧中間層だった。とはいってもモブが二十世紀に特有の現象とはいえないわね。モブの起源は十九世紀に遡るから」
雑多な貧民層が労働者階級として組織化され終えた十九世紀末は、帝国主義の時代でもある。階級化が進行するにつれて、そこから脱落する者たちも急増し、そして階級脱落(デクラセ)した群衆はモブカしていく。モブの出身階級は労働者にとどまらない。貴族やブルジョワや農民や都市貧民からもモブは生じ
431頁
ている。
433頁
「帝国主義化によって形骸化し空洞化していた国民国家と政党制、議会制民主主義が世界戦争の衝撃で崩壊した点。塹壕世代に蔓延した大衆ニヒリズムが大戦間の文化と政治に浸透していた点などの認識は、カウフマンさんとそれほど変わりません。しかし行動的ニヒリズムの評価は違いますね。
人間主義と進歩主義が十九世紀精神だったとすれば、二十世紀精神はニヒリズムと行動主義だから、行動的ニヒリズムの外に希望を見ようとするのは幻想です。ナチズムに勝利したアメリカニズムは自由と民主主義、啓蒙的理性と進歩主義などに体現された十九世紀精神の復興者のような顔つきをしていても、そのナイツは行動的ニヒリズムの消費社会的な凡庸化と微温化にすぎません。われわれ二十世紀人は時代的な宿命である行動的ニヒリズムに、倒錯したナチズムとボリシェヴィズムや微温的なアメリカニズムとは異なる可能性を見出すしかない」
老婦人が面白がるように問う。「レーム派に親近感を抱いたハルバッハを、あなたは評価するのか
434頁
しら」
「同時代のアヴァンギャルドやモダニズムと比較して、『実存と時間』のハルバッハ哲学は折衷的ですね。塹壕を埋めた産業廃棄物さながらの屍体の山に圧し潰され、塹壕世代は人間という理念の絶滅を否応ないものとして体感した。表現主義をはじめとするモダニズムとは、廃棄物にまで解体された青年たちによる近代芸術の破壊運動です。しかしハルバッハは、頽落した人間にも本来性に覚醒することが可能であるかのように語った」
「そうだとして、ナチズムでもボリシェヴィズムでもない行動的ニヒリズムの可能性とは」
「この夏のことです、スペイン内戦を共和国側で戦ったフランス人青年の運命について知る機会を得たのは。彼は共産党でもド・ゴール派でもない立場で対独抵抗運動(レジスタンス)を、大戦後はピレネー山中で……
435頁
カウフマンの言葉の真意を確認してみる。「上からの命令に唯々諾々と従った小役人が、アイヒマンだというのは間違いなんですか」
「わたしの本を読みもしないで、アイヒマンは凡庸な小役人だというのがカウフマンの主張だと触れ廻るような連中も多いけど、もちろん違いますよ。被告席のアイヒマンによれば、第三帝国ではヒトラーの意思が法で、それに従うことが道徳的だった」
カウフマンが裁判で驚かされたのは、アイヒマンがカントの道徳哲学を引用したことだったという。アイヒマンは主体性のない小さな歯車ではない。法そのものであるヒトラーに意思に主体的に、できる限りの熱意で応えきること。そのために持てる能力を限界まで傾注すること。大衆的人間(マッセンメンシュ)が渇望する地位や栄誉の獲得は、そうした懸命の努力の結果にすぎない。
「反ユダヤ主義のモブを免罪するつもりなどありませんよ。ガス室という絶対悪には、ユダヤ人の絶
436頁
滅に向けて作動する巨大装置と、その効率的な作動に懸命な努力を払う大衆的人間(マッセンメンシュ)の大群が不可欠だった。ユダヤ人の絶滅はモブの痙攣的な直接暴力ではなく、大衆的人間(マッセンメンシュ)の組織された機能的暴力の産物さったの。絶対悪はユダヤ人憎悪の狂気からではなく、凡庸な悪の累積から生じてくる」
「権力を獲得して以降、ナチ党の中枢から古参幹部が姿を消していくのと同じ光景が、同時期のポリシェヴィキ党でも見られましたね。モスクワ裁判が終わる一八三八年には、スターリン一人を例外としてレーニン政治局の全員が粛清裁判で消えていた。国外追放されたトロツキーも一九四〇年には、スターリンが送った暗殺者に殺害されている。一九三〇年代を通してソ連共産党は、モブ的な革命家の組織から大衆的人間(マッセンメンシュ)のメンタリティを持つ行政官僚の群れに変貌していく」
「感情移入の前提は超越論的自我、この私と同じような外見の物体が現象学的に還元された世界に登場することですね。私が悲しむときと同じような動作をそれが見せるとき、私は感情移入して、それをこの私と同じような主観、他我であることを了解する。しかし、この事例は不完全で曖昧です。そうして私はそれを私と同じ外見であると見なしうるのか。そのためには私はあらかじめ、それから見えるような私の外見を知っていなければならない」
「鏡は」わたしは尋ねる。「鏡に映る自分の像と、それの外見が一致すれば」
「そう、問題は鏡像だ。とはいえ鏡の発明は、人類史の全体からは最近のことにすぎない」
「ナルシスはどうかしら」水面に浮かんだ美少年に恋して見つめ続け、最後は水仙に変わってしまう
437頁
ナルシスの神話がある。
「水鏡も事例として必然性に欠けるね。考えてみよう。それが私の前に現れる。私はその瞳を覗きこむ。そこにはなにかの像が映っている。私が顔を顰めるとその像も表情が変わる。笑っても同じことだ。私はそれの瞳に映る像を、このようにして私の顔であることを直観する。ひいてはそれの瞳に映る私の外見を。このようにしてようやく、私はそれの外見が私の外見と同じであることを知る」
「瞳の事例はともかく、その先の論理は感情移入説と変わらないようね。それが哀しいときの私と同じ表情を見せるとき、私はそれに心があることを知る。そのことが類推なのか、それとも直観なのかは意見が分かれるにしても、このようにして私は他者の存在を、すなわち私とは別の超越論的自我の存在を知る」
カウフマンにカケルが反論する。「しかし、そのようにして現れる他者は私に与えられた現象ですね。私の世界にあらわれた他者の瞳には私が映っている。その私は他者にとって現象にすぎないとすると、世界を現象として直観する私と、他者に現象として直観される私は同じ私なのかどうか。
ここで奇妙な入れ子構造が生じてきます。他者の瞳に映る私の瞳には他者が映っているに違いない。そのようにして無限後退がはじまる。外の世界を還元して得られた超越論的主観性の世界は有限で内側に閉じられています。現象の背後には実在もなければ物自体もない。しかし、発見された他者の瞳には無限が宿されている。内に閉じられた有限の現象世界の裂孔こそが他者です。その裂け目からは認識不能の禍々しい外部が不気味な貎を覗かせている」
老婦人が頷いた。「わたしはヘーゲルでもフッサールでもない現象学者を自称してきたけれど、あなたも同類のようね。それはそれとして、では穴の開いた現象的世界はなおうなるの。私と同じ外見のそれは無数だし、超越論的主観性の世界は無数の他者で穴だらけになってしまうけど」
438頁
「だから他者は隠蔽されうるんですね。瞳から目を背けてしまえば、それは人間の外見をした物にすぎない」
「そうね。大衆的人間(マッセンメンシュ)の典型としてのアイヒマンの世界に、他者としての他者は存在しなかった。対話する他者を持ちえない者の特性は無思考です。アイヒマンは人が無数の、それぞれにまったく異なる他者たちと世界を共有していることに無自覚だった」
「モブ的なメンタリティには、失われた他者の存在が影を落としています。その喪失感からモブたちは逃れられない。モブの暴力性と残虐行為は、索漠とした世界に一瞬でもリアリティを回復させようとする痙攣的な欲望の産物です。
嗜虐者は他人の血で手を真っ赤に染め、苦痛の呻き声を耳にする瞬間にだけ他者と世界のリアリティを実感できる。しかし大衆的人間(マッセンメンシュ)に、そうしたサディズム的な傾向は稀薄ですね。アイヒマンは絶滅計画を効率的に進めるための画期的なアイディアを思いつき、ひたすら計算を重ねた。しかしモブや大衆的人間(マッセンメンシュ)による他者の隠蔽と世界喪失は、いずれにしても結果にすぎません」
「そういうことですか、結果というのは」
「超越論的主観性が無数の他者たちの存在で穴だらけにならないように、私と他者たちが共有する世界と間主観性が仮構されます。私にとっての私と他者にとっての私が同じ私であることを前提として。しかしそれは他者から他者性を剥奪し、この私の固有性を放棄することであって、他者と世界をめぐる臆断(ドクサ)への退行に他なりません。見える通りにある世界のなかに、他者も見える通りにいるというような。
しかし他者の他者性を隠蔽することで修復された世界は、常に危機に晒されています。あるとき不意に、無限を宿した他者が現前してくるという危機に。仮構された間主観性が崩壊に瀕するとき自己
439頁
防衛のために生じるのが、たとえばモブや大衆的人間(マッセンメンシュ)による他者の隠蔽や抹殺です」
同型的で同質的な私たちが一人一票の権利を行使する、たとえばワイマール共和国のような議会制の危機と亀裂から、ナチの全体主義大衆運動は湧き出してきた。カケルの主張を敷衍すれば、民主主義と権威主義は他者の他性を否定する二つの様式ということになる。
「では他者の他性から目を背けることなく、人が人と本当に出遭うには」カウフマンの口調が鋭い。
「交換です。それの瞳を見ると、そこに映った顔が自分を見ている。このとき私は、見られた私としての外見的な私を発見すると同時に、私を見ている他者を発見し、ひいては私と他者が共有する世界を発見する。ここで体験されるのはまなざしの交換です。私は他者を見ていると同時に他者に見られている、他者は私を見ると同時に私に見られている。こうして二つの私が交換され、この私と、その他者が見ている私の同一性が確信される。同時に私と他者の相互性もまた」
それでも視覚的な交換、まなざしの交換は根本的に不安定だ。かおおうじて得られた相互性も無限の底に呑まれてしまう危険性を回避しえない。それを支えるのが触角の交換だとカケルはいう。手と手を握りあうとき、私はそれに触れていると同時に触れられている。私が握るとそれは握り返してくる。触角の交換には無限をめぐる罠が存在しない。
「視覚の交換は触角の交換に、知覚の交換は物の交換に、さらに言葉の交換にも転化しうる。財の移動には交換と贈与と強奪がありますね。ゴリラやチンパンジーなどの類人猿にも贈与と強奪は観察されますが、交換は人間に固有です。言葉の発明は意識と表象の世界を人間にもたらした。意識は本性として独我論的だから、他者をめぐる難問に人類はつきまとわれることになる。抜本的な解決策は交換でした」
カウフマンは議論を愉しんでいるようだ。「言葉の交換を重視する点は賛成だけど、性行為を含む
440頁
触角の交換や経済行為としての財の交換は家(オイコス)に属する事柄で、公共空間での討論とは次元が違う。市場(アゴラ)での言葉を用いた売り買いには行動(アクション)の要素があるとしても、財の交換も大規模化すれば頽落の運命をまぬがれられない」
「交換が生産に組みこまれると交換の他性は浸蝕されはじめ、最終的には資本主義市場経済に呑まれて他性は完全に失われてしまう」
「その通り」
頷いた老婦人を見て、わたしは話を変えることにした。
441頁
「ナディアは理性の真理と事実の真理の違いがわかるわね」
「ええ」大学で勉強したことがある。
ライプニッツによれば理性の真理とは、球は中心からの距離が等しい面に囲まれた立体であるなど、概念にかかわる真理だ。ただし理性の真理でも数学の公理や命題のような真理と、天動説や進化
442頁
論のような科学的真理とは水準が異なる。事実の真理は実在にかかわることで、たとえばライプニッツは一六四六年にライプチヒで生まれたなど。科学的真理も事実の真理も可変的だが、ただし可変性の水準は異なっている。
カウフマンが続けた。「理性の真理の真理性は議論の余地がなく絶対的かつ強制的です。たとえ宗教裁判の恫喝に屈してガリレオが天動説を翻しても、真理は真理それ自体の力で偏見や誤謬を覆していく。しかし事実の真理に絶対的な強制力はない。事実の真理は出来事や環境に関係し目撃や証言に依存する。理性の真理を語るのが哲学者や科学者だとすれば、事実の真理は歴史家や裁判官、ジャーナリスト、レポーターなどに担われる。もちろん、事実の体験者による証言が重要であることはいうまでもないわね」
「では大量作買い(ジェノシード)否定論が勝利することもありうると」
老婦人は考え深い表情で頷いた。「歴史家や裁判官が本分を忘れて政治的意見に左右され、公正であることを放棄してしまえば。だから警戒を怠るわけにはいかないのよ。あなた、ル・モンドに乗った否定論者の文章は読んだかしら」
443頁
「ヒトラーはユダヤ人の絶滅を命じていないとか、アウシュヴィッツにガス室は存在しなかったとか、ユダヤ人は六百万人も死んでいないとか、こうした虚偽の否定論のほとんどは愚直に主張する。自分の嘘を本気で信じこんでいる著者も多い。ようするに虚偽を真剣に主張する。けれども『ホロコーストの神話(ミス)』の著者は違う。この本の目的はユダヤ人の大量虐殺(ジェノシード)をめぐる事実の真理に、それとは異なる事実の真理を対置するところにはない。真実と虚偽、本当と嘘の区別を消去してしまうことが目的なの。
『地下室の手記』の主人公は、〈2×2=4〉に、すなわち理性の真理に唾を吐く。真理の絶対性と強制性が、自由を抑圧しているように感じられて我慢できないから。これが事実の真理の場面になると、モブ的な陰謀論になる。ヒトラーは本気で陰謀論を信じこんでユダヤ人を憎悪していた。しかし大衆的人間(マッセンメンシュ)にはモブのような生々しい憎しみはないし、偽史や陰謀論への倒錯した情熱もない。興味があるのは安楽な私生活と組織内の昇進だけで、ある主張が事実かどうか、真実なのか虚偽なのか、そんなことはどうでもいいと思っている」
ナチズムの支持者たちはヒトラーの嘘に騙されていたのではなく、嘘と本当を区別する必要のない人々だった。大衆的人間(マッセンメンシュ)は信じたいことを信じるだけだから、目の前で陰謀論や否定論が真っ赤な嘘であることを論証して見せても意味はない。確実な証拠を突きつけても同じことだ。
そのような大衆的人間(マッセンメンシュ)を読者として書かれた本が『ホロコーストの神話(ミス)』で、著者のドルビニーは否定論者の信じる真の歴史を語ろうとはしない。歴史に客観性はない、真の歴史など存在しない、立場の数だけ異なる解釈があるだけだと嘯く。人は語りたいことを語り、信じたいことを信じればいい
444頁
のだと。
「ドルビニー的な歴史の相対化は、新たな忘却の穴を言説の形で掘ろうとしている。生き延びた者の証言冴え吸いこんでしまう、底に虚無を湛えた忘却の穴をね」
語り終えた老婦人に、カケルが挑発的なことを口にする。「ところで地下室の住人と同じですが、僕も〈2×2=4〉は嫌いですね」
「自由とは〈2×2=4〉といえる自由だ、という『一九八四』の主人公の言葉はどうかしら。不可疑的な真理の比喩としては、加算も乗算も意味的に同じだけど」
「あの主人公とは反対で、われわれは生まれたときから〈2×2=4〉を強制されてきたから。そこには鎖の鉄環さながら無数の真理だの法則だのが繋がっていて、唯物史観の歴史法則までがある」
「豊かな社会は産業主義に、産業主義派科学技術に、科学技術は理性の真理に支えられている。豊かな社会の抑圧と闘うには〈2×2=4〉を拒否しなければならない。そんなことをいう若者は昔もいまも少なくないわね。昔の右翼学生はハルバッハの『実存と時間』が参照先で、最近の左翼学生はマルクーゼかしら。わたしも〈2×2=4〉のような真理は空虚だと思うけど」
「本質直観に示されるように、イデアルなものはリアルなものから導かれます。主観にたいして明証的に与えられるリアルなものは現象で、現象の背後にはなにもない。実在も物自体も。自らは現象することなく、すべてを現象させるものとしてのハルバッハ的も存在もまた。
われわれは交換によって他者の存在を確信し、同時に他者と共有する世界の存在を確信する。知覚できる世界から情報として与えられる世界へと、確信の層は重畳していく。しかしいずれも信憑にすぎないから、世界は常に崩壊の危機に瀕している。世界の根本的な不確実性の予感が〈2×2=4〉への不信を生じさせるんです」
448頁
荒野で出くわした他者とは、言い換えれば同じ神を信じない者、同じ神を崇拝しない者だ。あるいは同じ祖先を持たない者で、このような他者は掟を共有していないから無制限の暴力が発動されうる。交換が成就して物が暴力を吸収するとき、そこには平和の法が一時的にしても成立する。平和の法は無法状態を法の世界に導くための最初の一歩だから、交換は世界に法をもたらす行為でもある。
「そうとは限りません。物の交換による平和の法の裏には、暴力の交換を秩序化するための抗争の法が生じてくる。同害報復の原理です」
449頁
報復は被害感情を満足させるために行われるのではない。被害感情は無制限の報復を求めかねないが、それは厳重に禁止される。同害報復は被害者の救済や被害感情の解消が目的ではなく、失われた均衡の回復のためになされる。言い換えれば正義の回復のために。
同害報復とは簡単にいえば「目には目を、歯には歯を」の法だろう。一人を殺された一人を殺すことが許される。それは権利であると同時に義務でもあり、数名の外来者によって一人の村人が殺害されたなら、外来者の一人を殺すことで崩れた均衡を回復しなければならない。
「正義とは均衡であって、崩れた均衡を回復することが正義だという観念は共同体の掟にも見られます。ある成員の破壊や暴力行為のために共同体の秩序が脅かされたとき、共同体の慣習法による対処は罪人をさばいて罰を下すというよりも、ムだれた均衡を回復することに主眼がある。均衡回復の原理が共同対外の他者に適用されると同害報復の義務が生じます」
ようやくカケルのいわんとするところが呑みこめた。物の交換と行為の交換の違いは明らかで、物の交換が失敗するときに暴力という行為の交換がはじまる。物の交換が平和の法を生じさせるように、暴力という行為の交換からは抗争の法、戦争の法が生じてくる。未開社会にみられる儀礼的戦争は戦争の法に規制される。
「儀礼的戦争は国家を生まないための知恵の産物だという人類学者もいますね。いずれにしても個人と個人、集団と集団のホッブズ的な戦争状態が人類史において一般的だった事実はない。戦争状態による共倒れを回避するために契約がなされ、国家が生じたという議論は根拠の稀薄な空想の産物にすぎません」カケルはホッブズの社会契約論を一蹴した。
450頁
わたしは質問した。「だとして交換の本質とは」
「二重化とずれだ。ある物と別の物が二重化されるが二重化は必然的にずれを生じる。交換の二重性が等価交換と、そのずれが不等価交換として意識されるように。しかし交換が交換としてなされる限り不等価交換は等価交換に、ずれはふたたび二重化に回帰していく」
誘拐の原理的考察でカケルが等価交換と不等価交換という言葉を用いたとき、わたしは常識的な意味で理解していた。しかしそれは、交換の本質の現象学的直観から導かれていたようだ。
青年が続ける。「二つの犯罪は交換されることで二重化するけれども、そこには必然的な差異が生じている。誘拐と殺人は等価ではないから。二つの行為の交換は不等価交換で、この二重化はずれをともなわざるをえない。したがって、〈誘拐と殺人の交換犯罪〉の本質は誘拐と殺人の二重化とずれに
451頁
ある。生じたずれは、またしても二重化されるだろう」
少し間を置いてから老婦人が口を開いた。「均衡こそ正義だというあなたの主張には賛成できないわね。同害報復では善の問題は棚上げされたままだし、正義とはあくまでもポリスの、公的世界の原理だから。均衡が正義なら等価交換という経済行為も正義になる。しかし経済(エコノミー)は語源的にも家(オイコス)の世界に属している」
「同じ神を信仰し、同じ伝統的規範を共有する共同体の内側でしか、善なるものは成立しません。人類共通の善が存在しうるのは、人類が対五つの共同体に統合されるときでしょう。しかし外のない唯一の共同体とは、いったん収監されたら絶対に出ることのできない、放免も脱獄も不可能な監獄と同じですね」
「ナチは六百万人のユダヤ人を殺した。あなたの主張では同害報復の正義のために、ユダヤ人は六百万人のドイツ人を殺さなければならないことになるけど」
「集団間の戦争のような大規模すぎる加害と被害では、同害報復が困難な場合もある。そんなときは均衡の回復のために物質的な補償が要請されます。六百万の屍体と均衡する重さの補償とはなんだろうか。第二次大戦直後の歴史条件からして、その解答は明らかでしょう」
「第一次大戦後のヴェルサイユ条約の場合と同じような高額の賠償金を、ユダヤ人はドイツに要求すべきだったと」
「いいえ、一方に六百万の死者を乗せた天秤が水平になるために、他方の皿に載せなければならないのは土地です。ユダヤ人国家を建設するために必要な土地をドイツに要求すること。カウフマンさんが語るように、国家しか人としての権利を保証できない以上、ユダヤ人は自身の国家を持たなければならない。そのための土地を提供する義務を負っているのは、六百万のユダヤ人を虐殺したドイツ国家で
452頁
す。
もう一点、第二次大戦中に政府がドイツに協力し、ユダヤ人絶滅に加担したのはフランスだけです。賠償としてユダヤ人が要求する土地には、フランスが領有権を主張するアルザスとロレーヌを含めるべきでしょうね」フランス人としては容易に認められないようなことを、この青年は平然という。
老婦人はしばらく考えこんでいた。「なるほどね。シオニストのパレスチナ中心主義に反対していたわたしも、そんなことは思いつきませんでしたよ。ドイツやフランスにユダヤ人のための領土を要求することなんてね」
「それはユダヤ人のためであると同時にドイツ人の、補足的にはフランス人のためでもある。ドイツ人によるユダヤ人絶滅の企てはたんなる巨悪ではない、ニュルンベルク法廷では人道に対する罪という新概念が持ち出されました。この悪の当事者であるドイツ国民は容易に赦されない。またユダヤ人もドイツ人を赦すわけにはいきません」
わたしは思わず問いかけていた。「でも人は謝罪することも、それを受け容れて罪を赦すこともできるわ。でなければ世界は、暴力と報復の際限ない応酬に呑みこまれてしまう」
青年がわたしを見た。「謝罪と赦しによる秩序の回復は、加害者と被害者が同じ共同体に属する場合に限られる。『目には目を』の同害報復は、多数の共同体を包摂する帝国の法として歴史的に成立した。同じ神を信仰しない共同体と共同体のあいだに生じた加害と被害には、謝罪も赦しも不可能だ。同害報復が秩序回復のために原理化されたのは、だからなんだ」
人類は今日でも単一の共同体に組織されていない。このことは人権が主権国家に属する限りでしか保証されえない現実に端的に示されている。国家間の加害と被害を均衡化する原理は、依然として同
453頁
害報復とその変奏だ。ある国家が他の国家に加害行為を謝罪し赦しを得るとしても、それは二つの国家が対応の権利で単一化することを意味しない。前者の後者への従属が、それも軍事的政治的なそれを含むところの倫理的かつ精神的な従属が必然的な帰結となる。
454頁
「ユダヤ人の絶滅を他の暴力、他の悪から切り離して絶対化するカウフマンさんの議論では、絶対悪は異次元の彼方から地上に不意に降ってきたようです。絶対的な悪には共同体内的な赦しも共同体外的な同害報復も不可能だとすれば、正義は原理的に回復されえないことになる。しかし、ユダヤ人の絶滅は最初から計画されていたのではありませんね」最終的解決と称された計画が決定される一九四二年までは、マダガスカルやウラルの東への大量追放が検討されていた。「特殊行動隊(アインザッツグルッペン)による東方占領地での大量銃殺が限界に達した果てに、いわばなりゆきで絶滅収容所での大量虐殺(ジェノシード)が決定された。ただし決定の経過は無計画的でも、その実行は精密機械の作動さながら計画的に遂行されていく」
456頁
「アイヒマンのような大衆的人間(マッセンメンシュ)による凡庸な悪は、おのれの行為の意味を思考しえないところから生じる。大衆的人間(マッセンメンシュ)には他者が不在だからですね。先ほどの議論に戻るようですが、私も同じでも私とは異なる多数の他者がいるということ、ようするに人間の複数性の認識は自明でも必然的でもありません。私は一瞬一瞬、かろうじて他者たちを、人間の複数性を捉えているにすぎない。ときとして均衡は大きく傾いてしまう。
大衆的人間(マッセンメンシュ)は他者が動く人形のようにしか実感できない。人形のあいだに紛れこんで、それでも不都合なく生きられるように訓練された私が、もしそうした条件下に置かれたなら、平然と青酸ガス放出のボタンを押すでしょう。複数性は人間にとって無条件的な前提ではない。ナチズムによる複数性の否定が絶対悪だとカウフマンさんはいう。しかし複数性の否定、現象学的には間主観性の成立不能化は前提であって結果ではない。だから問題は絶対悪ではなく観念悪なんです」
「観念悪とは」
「他者の喪失は他者と共有する世界の喪失ですね。他者喪失による世界喪失を肥大化した観念で倒錯的に補塡すること、それが観念悪です。倫理や正義の前提は他者が存在する世界だから、倒錯的な観念家の裡では倫理も正義も消去されている。それが逆説的にも正義観念の無制約的な肥大化を招いてしまう。そのために世界が滅びようと、私は正義を貫き通すというような。
それほどまでに世界が軽いのは、あらかじめ世界が喪われているからです。あるのはリアリティの希薄な偽の世界、世界のまがいものにすぎない。この不快で息苦しい偽物の世界を爆破する口実とし
457頁
て、観念家は過剰な正義観念を担ぎ出そうとする」
「そうね、他者がいなければ世界はない。世界は人と人の間に存在し、人とひとを結び付けると同時に引き離すものだから」
「現実的世界を喪失した観念家の真理は被害者意識、被害感情に染められている。被害を蒙った事実をめぐる意識は、失われた均衡の回復を、すなわち正義の回復を求める。それが不可能であるとき、被害の意識は自己言及的に無限累積されていく。反対物に転化するまでに肥大化し過剰化した正義観念は、被害感情の絶対化から生じます。
先ほどの話にも出たように全体主義運動は二つのタイプに支えられた。古参ボリシェヴィキや突撃隊(エスアー)の体制破壊タイプと、スターリニスト官僚や親衛隊(エヌエス)の体制維持タイプですね。ようするに反逆者と能吏です。前者の暴力性は空虚な世界への敵意から湧き出してくる。しかし後者の残忍性はソ連の秘密警察やナチのゲシュタポのように、いわばメカニカルです。前者が憎悪と破壊衝動から虐殺に走るのにたいし、後者は暴力の効果を精密に計算しながら犠牲者を消去していく。前者の供給源がモブだとしたら、後者は大衆的人間(マッセンメンシュ)の群れから選抜されます」
「それで」カウフマンは少し苛立っているように見えた。
「ユダヤ人は言語に絶する被害を蒙った。しかしカウフマンさんも語るように、被害の事実は被害者の行動を無条件に肯定するわけではない。パレスチナ人を追放して土地を強奪し、主権国家としてイスラエルを建国したユダヤ人ナショナリストの言動は、この罠に脚を取られたとしかいえないところがある。そのように批判したカウフマンさんはシオニストのあいだで孤立し、『凡庸な悪』の刊行を機に排除されるにいたった」
「だからどうなの」老婦人の口調は険しい。
458頁
「複数性から出発することはできません。他者も他者たちと私が共有する世界も、奇跡のようにかろうじて与えられたものにすぎない。いつでも壊れうるし実際に壊れてしまっている。そこから観念悪が生じるのですが、複数性を前提にする議論では極限的な観念悪が絶対悪と名指しされてしまう。アイヒマンの処刑は絶対悪に対応する絶対罰ではありえない。その処刑は正義の回復のためになされた。六百万の犠牲者のために回復された正義はわずか六百万分の一にすぎない、それでもゼロではありません」
「絶滅という絶対的な事実を相対化することでナチを免罪していると、わたしは同胞から非難されてきました。あなたの主張にも同じ非難がなされて当然ね。アウシュヴィッツは起きてはならないことだった、絶対に」





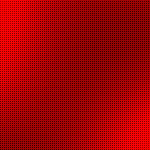



最近のコメント