橘玲著「日本で「家族解体」がなぜ進むのか」への批判
やや気になったので、『週刊文春』(2020年7月9日号)に掲載された記事、橘玲著「日本で「家族解体」がなぜ進むのか」への批判を書いておきたい。別に無視すればいいだけなのかもしれないが、彼のような見方が間違っていることだけは指摘しておきたい。そもそもペンネームを使ったうえで正体を隠して「社会評論」をする姿勢にヒトとしてまったく潔さを感じないので、こんな人物のいうことに反応しても意味はないのかもしれない。それでも、もう30年以上読み続けている『文春』に掲載された記事なので、その影響力を鑑みてこの論稿を書くことにした。実は、突っ込みどころ満載な記事なのだが、ここではとくに気になる記述についてだけ取り上げることにしよう。
「日本人はきわめて「個人主義的」なのです」
まずは、「常識とは異なって、日本人はきわめて「個人主義的」なのです」という記述について批判してみたい。「個人主義的」という意味がはっきり定義されているわけでないが、前後の文脈からみると、一人でいることを好む性癖のようなものを意味しているらしい。
この記述の前の段落に、「もうひとつは、明治維新とともに地域社会(故郷)をあっさり捨てて、都会で一人暮らしや核家族をつくるようになったことでしょう」と書いてある。ここで注意してほしいのは、この手の記述の不正確さについてである。まず、明治政府が意図的にそれまでの家族形態を破壊したのは事実だが、それは明治政府に特有なことではない。「近代国民国家は、多かれ少なかれ「家族国家主義」的なのである」という上野千鶴子の指摘がある。1994年に刊行された『近代家族の成立と終焉』の92ページにこう書かれている。この家族国家主義は家を国家の統制に直結するために邪魔になる中間集団を解体したのだ。その結果として、家族の共同体からの孤立が進み、明治期に入って親子心中が増加した。家族の問題も国家の問題と直結している。だが、明治の日本政府がとったのは家族の自然性を不可侵のものとみなして、その起源を問うことを禁止することであった(同, p. 96)。それによって国家による家族の搾取を隠蔽しようとしたのだ。
他方、一人暮らしについては、むしろ例外的であり、一人暮らしと明治政府の政策はまったく無関係だ。一人暮らしを日本人が好んだという証明にもなっていない。むしろ、親子心中の増加を考えると、一人暮らしをさせるに忍びない親が子どもを道づれにするケースが増えたと考えるのが自然だろう。つまり、ここでの記述はおかしいのである。
さらに、紹介した記述のあとに、「ところが世界のなかで日本でだけ、戦後すぐの時期から、下宿、アパート、ワンルームマンションへと一人暮らしの文化が急速に広がりました」とある。「日本でだけ」と彼が判断するのは勝手だが、その根拠は提示されていない。むしろ、この問題はアーキテクチャの問題を中心に論ずべき問題であるとだけ指摘しておこう。それを知りたい人は、山本理顕著『権力の空間/空間の権力:個人と国家の〈あいだ〉を設計せよ』を読むことを勧めたい。まあ、わたしからみると、橘は勉強がまったく足りないのである。もちろん、「イエ」という日本の制度に対する認識についても、彼がどの程度理解しているのか、大いに心配になる。
「日本人はどういうわけか、「一人」を孤独とは思いません」という記述も気になる。こう書く理由が提示されていないので、例によって牽強付会な説明にすぎないのだろう。ただ、読者が騙されないことを望む。
「そんな日本では、家庭のなかに複数の「世帯」ができてしまいます」というのも、怪しい記述だ。どうやら、夫婦や子ども間に関係の断絶があり、それを「世帯」という言葉で書き表そうとしているらしいのだが、これも牽強付会な乱暴な議論に思われる。
一夫一婦制について
つぎに、一歩一婦制に関する記述を批判してみよう。「「家族解体」の背景にあるのは、一夫一婦制の限界です」と書いたうえで、彼は「私たちは夫-妻-子どもという核家族を当然と考えていますが、これは西欧の近代化以降に生まれたきわめて「異常」な制度です」とのべている。
この記述も間違いだ。わたしが許せないのは、Todd, Emmanuel (2011) L’Origine des systèms familiaux, Tome Ⅰ, L’Eurasie, Gallimard=(2016) 石崎晴己監訳『家族システムの起源 Ⅰ ユーラシア上, 下』 藤原書店を読むこともなく、こんなバカなことを平然と書くことである。こんな輩の言説を掲載する『文春』もおかしい。要するに、マスメディアとしての責任を果たしていない。いま話題になっている、ディスインフォメーションやミスインフォメーションを「仲介者」を装うソーシャル・プラットフォームがどこまで「検閲」すべきかという問題を考えると、こうしためちゃくちゃな言説を載せること自体に大きな問題がある。
ここで、「おまけ」として、わたしが『官僚の世界史』に書いた内容を紹介しておこう。
****************************************************
長子相続は10世紀末以降、国家の不分割の道具としてヨーロッパでも台頭した。内因的要因としては、領土空間の稠密化で稀少財の移譲問題を解決するために土地の不分割性をとる必要性が高まったことがある一方、外因的要因としては、模倣や征服者集団による強制があった(Todd, 2011=2016 下, pp. 600-601)。こうした変化が教会の世襲化にも影響したと考えられる。
とくにこれを促すことになったのが西欧のカトリック教会であった。カトリック教会は、近接する血族間の結婚、夫が死亡した際、妻が夫の兄弟や近親者と再婚すること(レビレート婚)、子どもの養子縁組、離婚に厳しい姿勢をとったのである。その後、同教会は「妾囲い」を禁止、一夫一婦主義を促進するようになる。こうした背後には、家族の財産を子孫に渡すという相続を難しくて、自主的に教会に寄付させようとするねらいがあった。平均寿命が35歳程度の時代、相続は喫緊の課題であったのから、教会のこうした政策は教会への寄進増加に大いに寄与した。さらに、ヨーロッパの中世においては、母親が自分の娘に自身の姓をつけることが広く行われており、いわゆる核家族も13世紀までにヨーロッパの至る所に現れはじめていた(Fukuyama, 2012, p. 235)。寡婦は家族集団内で再婚したり、財産をその種族に戻したりするのが教会の政策で難しかったため、財産を自ら所有せざるをえなくなったわけだが、それは子どものいない寡婦からの教会への寄進につながったのである。とくに核家族化が進んだのはイングランド、デンマーク、オランダの絶対核家族と、パリ盆地、カスティーリャ、中部ポルトガル、南イタリアの平等主義的核家族だ(Todd, 2011=2016 下, pp. 62-621)。
****************************************************
読者にわかってほしいのは、少なくとも日本では、橘のようなわけのわからない、「匿名」とおぼしき輩が根拠に乏しい言説を書き、それを商業主義的なマスメディアが喧伝しているという事実である。だからこそ、気をつけてほしいのだ。こんな輩の書くもの自体、そもそも読むに値しないから無視すればいいのだが、だれかが注意しないと騙される人が出てしまう。
とくに、大切な記述に参考文献が記されているかは重大だ。たとえば、わたしが「論座」に掲載している記事では、意図的に参考文献を書き入れたり、URLですぐに参考文献にゆけるようにしている。こうした「良心」こそ、「もの書き」に必要な最低限のconscienceであると、わたしは信じている。逆に言えば、そんな良心をもたない橘のような輩には決して騙されてはならない。
その昔、庄司薫という小説家は『赤頭巾ちゃん気をつけて』で芥川賞をとった(わたしは彼に会ったことはないが、絵葉書をもらったことがある)。最後に、このタイトルにちなんで、「若者よ、気をつけて」ともう一度注意喚起しておきたい。



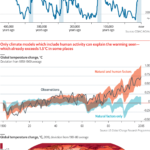




最近のコメント